ピックアップ

ベトナムにおける外国人労働者の雇用要件の緩和
弁護士 鈴木 萌 ベトナムで事業展開する日系企業は、現地法人での日本人の雇用を希望することが多くあります。この場合、ベトナムにおける外国人労働者の雇用に関する規制を守る必要がありますが、この規制に関して、先日法改正がありました。 まず、ベトナムで外国人労働者を雇用する場合、原則として、次のステップを踏む必要があります。 ① 外国人労働者の雇用予定の確認兼報告 雇用者が、外国人労働者の雇用予定人数を確定して、管轄機関に報告する手続です。管轄機関は、条件を満たしていれば、文書で外国人労働者の雇用を承認します。 ② 労働許可証(ワークパーミット)の取得 上記の外国人労働者雇用承認書を取得した場合に限り、申請することができます。ワークパーミットを取得するには、政令が定める取得条件を満たす必要があります。 ③ 在留許可(ビザ、レジデンスカード)の取得 ベトナムに入国して在留するための在留資格を得る手続です。 上記①②については、政令第152/2020/ND-CP号に定めがあり、この政令を改正する政令として、2023年9月18日に、政令第70/2023/ND-CP号(以下「政令70号」と言います。)が公布されました。 政令70号による変更点は多数ありますが、最も大きな変更点として、ワークパーミットの取得条件の緩和があります。 前述の通り、ワークパーミットの取得には一定の条件がありますが、外国人労働者を雇用する場合、原則として、当該労働者が、「管理者・業務執行者」、「専門家」、「技術者」の3カテゴリのどれかに該当することが求められます。 このうち、「専門家」及び「技術者」に該当するための条件について、変更がありました。 「専門家」及び「技術者」に該当するための従前の条件は、次のとおりです。 専門家 a. ベトナムで就労しようとする業務・職位に適合する分野を専攻とする大卒以上(あるいは相当)の学位、及びその専門分野における3年以上の勤務経歴を有する者 b. 又は、ベトナムで就労する予定の職位に適合する5年以上の勤務経験及び職業従事資格証明書を有する者 c. 又は、労働傷病兵社会問題省の提案に基づき政府首相が決定する特別な場合 技術者 a. 技術又はその他の専門分野について最低1年間以上の教育を受け、かつ、その専門分野において3年以上の実務経験を有する者 b. 又は、ベトナムで就労予定の職位に適合する業務に従事した5年以上の実務経験を有する者 従前は、原則として、「専門家」についてはベトナムで就労しようとする業務・職位に適合する分野を専攻とする大卒以上の学歴と、当該専門分野における職歴が、「技術者」については教育を受けた専門分野における職歴が、それぞれ必要とされ、学歴と職歴の分野的な連続性が求められていました。 しかし、特に日本では、教育課程での専攻が職歴や現職と結びついていない場合も多く、これが現地法人で日本人を雇用する場合にネックとなっていました。 今回の改正で、この条件が緩和され、「専門家」「技術者」どちらについても、教育課程での専攻分野と、職歴・就労予定業務との間の連続性の条件が廃止されました。 この点の改正は、ベトナムで日本人を雇用したい企業にとっては朗報と言えるでしょう。 なお、この部分の改正は、2023年9月18日に発効済みで、既に運用が始まっています。 以上

ベトナム労務管理における残業代計算
弁護士 原 智輝 工場などの従業員が多い事業形態において、その勤怠管理は重要項目の一つに挙げられます。特に、グローバルに事業を展開している企業においては、単に使用者(企業)と労働者の関係としてのみならず、昨今のSDGsなど社会に対する関係としても労務管理というものを考える必要があります。 ベトナムにおける勤怠管理については、例えば残業代に関する法令が労働法の中に定められており、以下のような基準で計算することとなっています。 【ベトナム労働法98条1項(割増賃金)】 ・通常の勤務日の場合は150% ・週休日の場合は200% ・祝日、旧正月、有給休暇時の場合は300% ここでいう、割増の対象となる賃金単価の計算方法ですが、政令(No.145/2020/ND-CP)55条1項に関連規定が置かれており、実労働時間から算出することとされています。そのため、一般的な労働者においては、月の労働時間単価が当月の祝日数、休暇日数などによって異なり得ることとなります。例えば、ある月の勤務日数が20日である場合と25日である場合とでは、前者の方が上記の150%などを乗じる対象の賃金額が高いということになります。 これを避けるために、一定の企業では就業規則内に残業(時間外労働)算出における毎月の勤務日数を固定の日数として定める場合も見受けられます。例えば、月の勤務日数はその月の実勤務日数にかかわらず、20日として時間外労働における割増賃金を計算するといった具合です。 注意点としては、基本賃金単価を下げようとして、1か月の勤務日数を30日など、法定の勤務時間を超過するような方法はとれないという点になります。労働法(105条1項)において、労働時間は1日8時間、週で48時間を超えることはできないため、1週当たり6日(48時間)の労働が最大となります。そのため、このような数値を超える勤務時間を就業規則で定めることはできません。 時間外労働に関する実際の計算においては、上記計算式を認識していない方も多いため、この機に一度就業規則の見直しや、時間外労働についての点検を行ってみてはいかがでしょうか? 以上

ベトナムにおける債権回収の実務
弁護士 原 智輝 1.はじめに 筆者はベトナムにて勤務を開始し、3年半ほど日系ベトナム進出企業の相談を受けてきましたが、3年前から相談件数の減らない項目の一つに債権回収の相談が挙げられます。 なぜ債権回収がここまでホットトピックになるのか、背景や事情は様々ですが、要約すると以下のようなものになります。 ・投資法、企業法等(No.59/2020/QH14)の改正により債権回収事業が禁止に ・ベトナムにおける法制度、司法制度の不透明性から企業が裁判所の活用に積極的でない ・ベトナム企業側の「待ってくれ」「お金がない」などの言い分に対応できていない 言い換えれば、司法面で裁判所などの機関を活用しづらいので、企業は自社で自力対応をしなければならない状況に立たされやすいのですが、ベトナム法制度が分からない、現地法人に法務担当者がいないため対応方法が分からないということが理由になります。 2.最低限押さえておきたいベトナムの債権回収に関する法制度 すでに他の記事等と重複している内容は割愛しますが、ベトナム事業における債権管理分野で絶対に押さえておきたい法律項目は以下のようなものがあります。 ・日越間の裁判所の判決には相互執行の関係がないので、取引契約書において、日本の裁判所を専属的合意管轄にすることは推奨されません。 ・ベトナムにおける提訴時効(いわゆる商事時効)は2年間とされており、債権の履行期を過ぎた場合に容易に商事時効を迎える事態が想定されます。 3.ベトナムでどう債権回収を試みるか(現場実感) さて、ようやく本題になりますが、このようなベトナムの状況で、いかにして現地日系企業が債権回収に臨んでいるのかというお話をさせていただきたいと思います。特別なことをしているわけではなく、泥臭い部分もありますが、法的な部分も解説したいと思います。 いわゆる債権回収の場面に出くわした場合、企業側がまず行わなければならないのが、債権債務関係の整理です。これは、履行期の債権がどのような資料から生じており、時効がいつになるのか、債権について裁判所等を活用しようとした場合の紛争解決機関の確認等です。よくある悩ましい事例としては、複数の取引関係があり、回収すべき債権総額は把握しているが、途中一部弁済等もあり、どの債権がいくら存在しているのかまでは把握できていない場合等が挙げられます。この場合、1年前からしばしば支払い遅延があったとなると、先の時効の問題にも発展するからです。また、一般的にはどうしても裁判所等を活用しにくいため、回収の肝は回収先との交渉になります。債権債務関係を整理することは、交渉の際に何を獲得目標にして、どのような話し合いをするのか、プランニングを行っていると言い換えることができるかと思います。 実際の交渉の場(打合せの場)では、プランニングに従った対応を採ることになりますが、基本的には債務者の資力に関する情報の獲得がマストです。しかし、当然ベトナム企業側も自社の財務情報を容易に開示することはなく、場合によってはいわゆる秘密保持契約書等を必要とする場合があります。また、銀行口座残高の開示が難しい場合には、本来あるべき預金残高以上の金額が口座内にあることや他社に対して債権を有していることについて代表者に表明保証をしてもらうことも考えられます。要するに誓約書をお願いするわけですが、法的な効果としては民事的なもの以上に、残高の情報が虚偽である場合、一部刑事上の詐欺罪を構成する余地も生じるため、債務者に対する責任の自覚を促すという効果が期待できます。 このように実際の現場では、様々な交渉を行いながら法的な取り決めに落とし込んでいく作業が行われているわけです。 4.自社の債権管理にご関心のある企業様へ 冒頭で触れましたとおり、ベトナムでは日本と異なり、自力対応を中心としたいわゆる予防法務の比重が極めて高いように思われます。売掛金の期限が到来してから弁護士に相談するというのが実情であるかとは思いますが、ご相談に来られた時点で「泣き寝入りが濃厚」のご相談が多いのも事実です。 そこで、弊所では、ベトナム事業における債権管理を自力で行えるためのサービスを用意しております。主に駐在員ご担当者様向けに、弁護士によるマンツーマンのコーチング形式にて、債権管理のノウハウ習得と自力による社内管理フローの構築をサポートさせていただくサービスです。外国かつ法務という駐在員にとってスキルの習得やその運用に必要とされる時間を大幅に短縮させ/節約し、また将来の債権トラブルから生じる社内リソースやその際の弁護士費用/裁判費用などといった金銭的負担を軽減することを目的としております。 ご関心のある企業様におかれましては、弊所お問合せメールアドレス又は所属弁護士宛てに本サービスに関するお問合せをいただけますと幸いです。 以上

ベトナムにおけるプライバシーポリシー
弁護士 鈴木 萌 ベトナムにおいても、日本と同様に、事業活動の中で個人情報を取り扱うことが予定されている場合には、自社サイト等においてプライバシーポリシーを掲げることが一般的です。今回は、プライバシーポリシーに関するベトナムの法規制や、プライバシーポリシーの記載内容について、解説します。 1.プライバシーポリシーに関する法規制 (1) 個人情報保護政令 長らく、ベトナムには、日本でいう個人情報保護法のような、個人情報保護について網羅的に規定した法令が存在していませんでしたが、今般、個人データ保護に関する政令(13/2023/ND-CP。以下「個人情報保護政令」)が制定され、2023年7月1日に施行されました。 個人情報保護政令では、規制対象となる主体が以下のとおり区分されています。 ・「個人データ管理者」:個人データを処理(収集、記録、分析、確認、保管、修正、開示、結合、アクセス、追跡可能性、検索、暗号化、復号化、コピー、共有、送信、提供、移転、削除、破棄、またはその他の関連する活動を指す。)する目的、手段を決定する個人又は組織 ・「個人データ処理者」:契約を通じてデータ管理者に代わり、個人データの処理を行う個人又は組織 ・「個人データ管理及び処理者」:上記2者を兼ねている個人又は組織 上記のうち「個人データ管理者」と「個人データ管理及び処理者」には、次の規制がいずれもかかります。 (a) 同意取得(11条) 個人データの処理にあたって、データの種類、処理目的、処理組織(個人)、個人データ主体の権利義務を明示して、データ主体の同意を取得することが求められます。また、同意の方式については、積極的な方法によることが求められており、沈黙やチェックボックスのチェックを外さなかった場合のような消極的な同意が排除されています。 (b) 個人データ処理通知(13条) 原則として、個人データ処理開始時に、データ主体に対して、次の項目について通知を行うことが求められます。 ・ 個人データの処理目的 ・ 処理対象データの種類 ・ 個人データの処理方法 ・ 個人データを処理する組織又は個人 ・ 生じうる望ましくない結果と損害 ・ 個人データ処理の始期及び終期 なお、このデータ処理前のデータ主体に対する通知義務については、ここで規定されている事項につきデータ主体の同意を得た場合には、義務が免除されます(13条4項a号)。そのため、実務上は、要同意取得項目と要通知項目のすべてについて、同意の対象に含めることが予想されます。 (2) 電子商取引に関する政令 プライバシーポリシーに関しては、前述の個人情報保護政令の規制の他、次の規制が存在します。 電子商取引に関する政令52/2013/ND-CP 「第69条 消費者プライバシーポリシー 1. 消費者の個人情報を収集・利用する業者、団体、個人は、以下の内容の個人情報保護方針を策定し、公表しなければならない。 a) 個人情報の収集目的; b) 情報の利用範囲; c) 情報の保管時間; d) かかる情報にアクセスできる個人または組織; e) 情報収集管理組織の連絡先;消費者が個人に関連する情報の収集と処理について問い合わせることができる連絡先を含む; f) 消費者が情報収組織の電子商取引システム上で自分の個人データにアクセスし、修正するための方法およびツール。 2. 上記の内容は、情報収集前または情報収集時に消費者に明確に表示しなければならない。 3. 情報収集組織の電子商取引ウェブサイトを通じて情報収集を行う場合には、個人情報保護方針を当該ウェブサイト上の見やすい場所に公表しなければならない。」 上記は、「消費者の」個人情報を収集・利用する場合を念頭に置いた規制ですが、多くの企業では、プライバシーポリシーを作成・公表することで、この規制にも対応したい場合が多いと考えられることから、これらの要公表項目についても、プライバシーポリシーに含めることが考えられる。 2. プライバシーポリシーの内容 プライバシーポリシーを前述の規制を遵守するために使用することを考えた場合、プライバシーポリシーには、次の事項を含むのが適当と考えられます。 ① 処理対象データの種類 ② 個人データの処理目的 ③ 個人データを処理する組織又は個人 ④ 個人データ主体の権利義務(下記項目) a. データ処理内容等に関する通知受領権 b. データ処理に対する同意権 c. 個人データへのアクセス権 d. 同意撤回権 e. 個人データの削除権 f. データ処理への制限要請権 g. 自己の個人データ提供要求権 h. データ処理への異議申立権 i. 苦情、訴訟等の権利 j. 損害賠償請求権 k. 自己防衛権 l. データ主体の各種義務(個人情報保護政令10条) ⑤ 個人データの処理方法 ⑥ 生じうる望ましくない結果と損害 ⑦ 個人データ処理の始期及び終期(情報の保管時間) ⑧ 情報の利用範囲 ⑨ 情報収集管理組織の連絡先;消費者が個人に関連する情報の収集と処理について問い合わせることができる連絡先を含む ⑩ 消費者が情報収組織の電子商取引システム上で自分の個人データにアクセスし、修正するための方法およびツール。 なお、 ⑪ 個人データの保護措置 については、同意取得や通知が必須の事項とはされていませんが、個人情報保護政令26条において実施が求められていることから、記載しておいた方が望ましいと考えられます。 3. プライバシーポリシーの掲載方法 プライバシーポリシーの掲載形式については、上記電子商取引に関する政令の定め以上の制限はありませんが、ベトナム人向けに公表するものである場合には、ベトナム語で、ウェブサイトの見やすい場所(トップページから1クリックで遷移できる程度の場所に掲載することで問題はないものと思われる。)に掲載するのが適当と考えられます。 ベトナムでも、多くの企業において、プライバシーポリシーの作成・公表が必要となります。近時、ベトナムにおいても個人情報に関する意識が高まってきていますので、まだ作成していない場合には、作成することをお勧めします。

具体的にベトナム進出を検討したい人必見!どのエリアに進出する?
ベトナム進出の際、現地拠点をどこに置くかは、経営戦略上の重要な検討事項です。多くの日系企業は、通常、部材調達先、製品の販売先、労働者の採用といった様々な面からメリットとデメリットを検討し、北部もしくは南部を進出先として選択しています。ベトナム計画投資省のデータからも、海外からの投資先として、中部に比べて北部と南部への投資が多いことが分かります。中国との取引が多い企業は北部を、ASEAN諸国との取引が多い企業は南部を選択する傾向があります。 北部は首都ハノイに政府機関が集中しており、政府との交渉上利便性が高いと言えます。一方、南部はホーチミンを中心とした国内最大の経済区域であり、小売業・サービス業にとって魅力となっています。距離的には、ハノイ(北部)~ホーチミン(南部)間は約1,140km、航空機で移動時間は約2時間、陸路では約1,700kmで、鉄道での移動時間は約30~40時間となっています。 中部は北部・南部と比較すると、現状ではインフラ整備の面で劣っています。しかし、ビーチやホテル等を活かした観光産業や不動産開発の発展とASEAN諸国とタイ、インドを結ぶ物流拠点としての発展が見込まれています。 ※グラフのデータは『ベトナム計画投資省』参照 ベトナム北部の特徴 首都ハノイには、多くのベトナムおよび各国の政府機関、国際機関が置かれています。そのような公的機関との交渉が多い大企業は、北部に多く進出しています。 北部を選択するメリットとしては、経済面では、南部より若干割安で労働力が確保できること、部材の調達が比較的容易であること、今後の発展の余地が大きいこと等が挙げられます。政治面では、政府当局から情報を入手しやすく、交渉面での利便性が広く認識されています。 一方、デメリットとしては、電力が不足しやすいこと、通信インフラや道路の舗装状態も不十分である等、インフラの未整備な状況が挙げられますが、ODA事業によって、改善されていくと予想されます。現在のところでは、南部と比較すると裾野産業の集積は遅れています。 ベトナム北部へ進出した主な日系企業 大手メーカーに追従した部品メーカーが多く進出しています。 産業 日系企業 自動車 トヨタ、日野、ダイハツ、ホンダ 金属、自動車部品等 ブリヂストン、三井金属鉱業、共栄製鋼 二輪車 ホンダ、ヤマハ 家電 パナソニック 事務機 キャノン、ブラザー、京セラ、富士ゼロックス 電子電機機器 デンソー、豊田合成 小売業 イオン 食品 味の素 医療品 ニプロファーマ ベトナム南部の特徴 ベトナム最大の都市であるホーチミンは、最も経済活動が活発な地域です。メコン川流域(メコンデルタ)では、農水産物の収穫量も多く、海上輸送の重要拠点としても栄えています。特に、食品加工や繊維・縫製産業における進出企業数が多く、中小・零細企業も古くから進出していました。 南部を選択する第一のメリットは、経済的に最も活発・成熟した地域であり、ベトナム最大の消費市場を有することです。近年は特に、小売業やサービス業の進出が盛んにおこなわれています。さらに、ASEAN市場へ交通面でも利便性が高く、物流に関するインフラも整備されています。歴史を振り返っても、資本主義体制の導入が他の地域に比べ早く進んだことから産業基盤が整備されていることも魅力と言えます。 一方、デメリットは、外国企業の進出増加により、優秀な労働者の確保が困難になっている点が挙げられます。特に、中間管理職となる人材の不足に頭を悩ませている企業も少なくありません。また、過熱気味ともいえる不動産投資により土地価格が急騰しており、オフィスの賃料も年々上昇している状況です。 ベトナム南部へ進出した主な日系企業 現地の消費市場を目的とした企業が多く進出しています。 産業 日系企業 自動車 三菱、スズキ、いすゞ、マツダ 二輪車 スズキ 家電 パナソニック、JVC、三洋電機、ソニー、東芝 電子電機機器 富士通、矢崎総業、日本電産 小売業 イオン、セブンイレブン、ミニストップ 製薬 久光製薬、ロート製薬、資生堂 不動産開発、販売 東京急行電鉄 食品 丸善食品、エースコック、味の素、ヤクルト 外食 丸亀製麺、吉野家、すき家、大戸屋 インフラの整備状況 長期にわたる戦争の影響もあり、ベトナムでは産業基盤の整備が遅れています。日本のODAや世界銀行、アジア開発銀行(ADB)などの援助もあり、現在急速に整備が進められています。 現状では、特に電力の分野で他のアジア諸国に劣る印象があるものの、今後は多額の国家予算(日本のODA事業を含む)がインフラ整備プロジェクトに投入されることが予定されており、近い将来には大きな改善が期待できます。 道路敷設 総距離数では、タイ、インドネシア、フィリピンと比較して、ベトナムが下回っています。そして、ハノイ、ホーチミンなど都市部でも、道幅が狭く、かつ産業道路と生活道路が共用となっていることや、車・バイク・自転車といった路線区分がないことが多い為、通勤時間帯には渋滞が発生します。 経済回廊(「南北経済回廊」「中越経済回廊」「東西経済回廊」の3回廊)の完成後には、北部の中心であるハノイ、中分の中心であるダナン・フエ、南部の中心であるホーチミンは、インドシナ半島の各国と陸路で繋がることになり、国内の物流体制の大幅な改善が期待されます。東南アジア最長のハイバントンネル(ハノイ~ホーチミン~カーマウ間)の開通や南北高速道路(ハノイ~カント―)の建設も進んでおり、さらなる物流の円滑化と、地域経済開発の促進が期待されています。 鉄道 現在の鉄道の問題点としては、電化されていないこと、車両が古いこと、線路が劣化していること等が挙げられます。ハノイ~ホーチミン間については、現在の旅客列車では最短でも約30時間を要します。現在、ハノイ~ホーチミン間の高速鉄道計画が進んでおり、第1期(~2030年)は、ハノイ~ヴィン(グアン省)間とニャチャン(カインホア省)~ホーチミン間、第2期(2030年~2045年)は、ヴィン~ニャチャン間が完成する計画です。完成が実現すれば、ハノイ~ホーチミン間が10時間程度で移動できるようになります。 電力 ベトナムの主要な産業エネルギーは、水力発電と火力発電です。しかし、水力発電は、水不足の影響を受けやすく、電力不足の原因となっています。また、送電設備も全体的に老朽化が進んでおり、電力損失率が高くなっています。そのため、ほとんどの日系工業団地は自家発電設備を整えています。さらに、ベトナム政府も電力供給量の拡大に努めており、第8次国家電力マスタープランによると、再生可能得エネルギーの開発強化、送電線システムの改善と開発強化などが提案されています。 ※グラフのデータは『一般社団法人 海外電力調査会(JEPIC)』参照 空港 現在、国内には主な3つの国際空港(ハノイのノイバイ空港、ホーチミンのタンソンニャット空港、ダナンのダナン空港)が存在します。 南部では、タンソンニャット空港の大幅な需要超過を受けて、ホーチミンから約40km離れたドンナイ省のロンタインに新しい国際空港の建設が計画されています。新国際空港が完成すれば、現在のタンソンニャット空港は国内線の空港として利用される予定です。 港湾 ベトナムは、国土が南北に細長く、長い海岸線を有するため、多数の港湾が点在しています。しかし、ほとんどが河川港で大型船舶が寄港できる大水深港がなく、香港やシンガポール等での積み替えを余儀なくされており、時間とコストがかかります。日本~ベトナムを結ぶ航路も主にシンガポールや香港を一旦経由することが多くなっています。 急速な経済成長及び国内市場の拡大に伴い貨物需要が増大、需要に見合う港湾整備が必要となり、国際的な物流拠点として水深港を整備する必要性も大きくなってきています。2018年には、水深14mの大深度国際港であるラックフェン港が開港しています。 通信 ベトナムでは携帯電話が普及しており、利用料金も非常に安く、ホーチミン市内では、無料Wi-fiサービスを提供する飲食店等も多くなっています。ベトナム全土において通信環境は良好であり、企業によっては工場内のIT化も進んでいます。 ※ドイツの市場調査会社スタティスタ(Statista)調査データ ベトナムの工業団地 工業団地とは一定の区画された敷地に工業集積を図り、電力供給施設や通関事務所、居住用の団地等を設置し、効率的な生産を目的として設立されるものです。当該地域においては、外資系企業への優遇税制等、様々なインセンティブが設けられています。日系企業のうち、製造業の多くは、主要都市の近郊にある日系工業団地、またはインフラの整った日系以外の外資系工業団地やローカル工業団地に入居しています。 日系工業団地は、ベトナムのローカル工業団地に比べ利点が多いと言えます。例として、会社設立から投資申請、工場の操業まで現地日本人スタッフによるサポートが受けられます。この点は、初めてベトナムに進出する企業にとっては、大きな魅力となっています。 一方、ローカル工業団地は、土地賃借料の安さが最大の魅力です。ただし、日系工業団地と同レベルのインフラ、各種サポートを望むのは難しいのが現状です。しかし、ベトナム政府主導による外資系企業誘致政策の一環で、充実したサービス(日本語での支援を含む)を提供するローカル工業団地も現れています。 工業団地については立地条件、道路、電力、水、通信、管理、サービスなど千差万別であり、自社の許容レベルに合わせて検討することが大切です。 ベトナム北部 北部では、ラックフェン港の開発や高速道路の開通により、生産拠点としての魅力が増しており、外資系企業の進出が増えています。既存の外資系工業団地の販売区画もほぼ完売状態にあることから、ローカル工業団地への進出が目立っています。しかし、ローカル工業団地では、区画販売後に造成開発契約の遅れやインフラ整備にあたりトラブルが生じるケース、地理条件等の情報が不十分なケースもあるため、既に進出している企業への聞き取りや周辺調査、経験の豊富な日系の建設業者への相談が望ましいと言えます。 ※北部の主な日系工業団地 〇 日本ハイフォン工業団地(旧 野村ハイフォン工業団地) 〇 第一タンロン工業団地 〇 第二タンロン工業団地 〇 第三タンロン工業団地 〇 VSIPバクニン工業団地 〇 VSIPハイフォン工業団地 ベトナム中部 以前、中部には日系工業団地はありませんでしたが、東西経済回廊の開通などを見越し、近年日系を含む外資系産業の進出も増えてきています。工業団地をはじめとして、各種インフラや生活環境整備の一層の充実が今後の課題となっています。 ※中部の主な日系工業団地 〇 VSIPクアンガイ工業団地 ベトナム南部 南部は日系企業の進出の歴史も古く、最も多くの外資系企業が進出しています。日系をはじめ様々な工業団地が数多くあります。しかし、外資系企業の進出が相次いだことでホーチミン近郊の工業団地は常に人気が高く、希望してもなかなか入れない状態が続いています。特に、既存の日系工業団地は、ここ数年拡張部分も含め需要が高く、将来的な建設予定部分を除いてはほぼ完売状態となっています。 ※南部の主な日系工業団地 〇 アマタ工業団地 〇 VSIPⅠビンズン工業団地 〇 VSIPⅡビンズオン工業団地 〇 VSIPⅢビンズオン工業団地 〇 ロテコ工業団地 〇 ロンドゥック工業団地 その他:リース工場 ベトナム政府は、国内の裾野産業の育成を目指し、当該技術を供与する外資系企業の積極的な誘致を進めています。このため、部品産業等においては外資系企業、なかでも中小・零細企業の進出の増加が期待されています。中小・零細企業にとって工業建設はリスクが大きいため、注目されているのが「リース工場」です。 リース工場とは、工業団地内の作業スペースを、リース契約に基づき貸借して生産を行う形態で、安価な賃借料で作業スペースを確保し、機械や設備を持ち込むだけで、直ちに生産を開始できるという手軽さが魅力となっています。低コストでベトナムへ進出することが可能なため、今後も需要の高まりが予想されます。なお、日系リース工場は、人気が高いため空いていないことも多く、事前の調査が必要です。 明倫国際法律事務所では、ベトナム(ハノイ・ホーチミン)にも事務所を構えております。日本人弁護士はもちろん日本語ができるベトナム人弁護士、パラリーガルが常駐し、迅速的かつ適切に対応できます。今回、記載した内容のサポートはもちろんのこと、初期の検討段階から実際の設立、その後の運用支援まで、ワンストップで対応しています。また、コンサルティング会社では担うことのできない、発生したトラブルの解決、紛争対応などの対応は、もちろん未然に防ぐための企業戦略のコンサルティングサポートも可能です。「海外進出や販路拡大について広く知りたい」「現地の投資環境について全体像を掴みたい」等のご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

ベトナム進出を成功に導くポイントとは
知っておくべきベトナム情報 ベトナムの概要 ベトナム(正式名:ベトナム社会主義共和国)は、人口9,851万人※(2021年)、面積33.1万km2、公用語はベトナム語で、日本との時差は-2時間あります。南北に長く(約1,600km)、北部、中部、南部で特徴が異なります。 日本はベトナムと1973年に外交関係を樹立し、経済発展に関わる人材育成の為の技術提供や、交通や生活のインフラ整備の資金提供などを積極的におこなってきました。ベトナムにとって日本は最大の支援国のひとつであり、政治、経済、安全保障、文化・人的交流など幅広い分野で連携しており、親日である国民が非常に多くなっています。 ※『ベトナム総合統計局』より参照 ベトナム北部 ベトナム北部は、政治・文化の中心である首都ハノイがあり、政府や国連などの機関が集まっています。インフラ整備や大型商業施設などの都市開発が進んでおり、日系企業や外資系企業の進出増加に伴い在住外国人も増えています。近年は所得増加から、単なる製造拠点ではなく、消費市場としても注目を集めています。 ベトナム中部 ベトナム中部は、近年リゾート地として人気の高いダナンを中心に観光業やIT産業が集約しています。ダナンはハノイ、ホーチミンに次ぐ第3の都市となっており、近年では、賃料や人件費の安さから、日系企業の進出も少しずつ増加傾向にあります。今後、新たな生産・開発拠点や大型商業施設、ホテルなど多くの企業の進出が見込まれています。 ベトナム南部 ベトナム南部は、ベトナム最大の商業都市ホーチミンを中心に商業および観光業が活発におこなわれています。ベトナム経済を牽引する都市として発展しており、日系企業をはじめ外国企業は南部に多く進出しています。現在では、都市開発・経済発展が進み、外資系ホテルや高層オフィスビル、大型商業施設、分譲マンションが建設されています。 ベトナムの商習慣に対する3つの対策 ベトナム人・ベトナム企業の商習慣や傾向を知っておくことは、ビジネス上のトラブルを事前に防ぐ為に重要です。 ① スピーディーな意思決定 日本人は、極力失敗のリスクを減らそうと計画や事前準備に長い時間をかけます。一方、ベトナム人は、直感的に物事を捉える傾向があり、トップダウンでスピーディーに実行に移していきます。その為、日系企業は計画の策定等の事前準備に時間をかけ過ぎているという印象を抱かれる傾向があります。 また、ベトナム人・ベトナム企業は、短期的な利益回収を求める傾向があり、長期的・安定的な利益よりも、投資額の早期回収に重点が置かれます。 このように仕事の進め方についても違いがあることから、なるべく意思決定権のある人が商談に参加する、方向性をあらかじめ決めて商談に臨むなど、スピーディーな取引を心がけましょう。 ② 報告・連絡・相談の徹底 日本では基本となっている報告・連絡・相談が、一般的に海外は、希薄な傾向です。ベトナムも例外ではありません。そのため、ベトナムに子会社のある日系企業でも、現地の事業状況についての適切な報告がなく、会社の状況がみえなくなってしまうこともしばしば見受けられます。また、取引相手であるベトナム企業に問合せしたものの、なかなか返事がかえってこないということ等は日常的に起こります。 また、部下は上司の判断を仰ぐというビジネス上の常識も、ベトナムにおいてはいまだ浸透していません。その為、従業員が自分の判断で勝手に進めたり、1人で悩みを抱えこむケースもみられます。このような事態を招かぬよう、現地の従業員に対しては、研修や指導を通して、報告・連絡・相談の必要性を認識してもらい、コミュニケーションや仕事の進め方のルールやその体制を構築することが望まれます。 ③ 余裕をもったスケジュール管理 海外をはじめとする諸外国では、日本に比べて時間に正確に行動するという意識が一般的に希薄です。ベトナムでは、交通渋滞が日常化しているという事情もあり、ビジネスでも、集合時間や会議時間に10~30分遅れることが多くあります。また、納期遅れもしばしば発生するため、ベトナム現地にて製品の製造をおこなう場合には、こまめに進捗を確認し、納期を守ってもらうような働きかけが重要です。場合によっては、多少の遅れを見込んだ上でスケジュールを立てておくことも必要です。 また、ベトナム人は、家族との時間を非常に大切にします。ベトナムでの有給休暇取得率は100%に近く、年に1回以上は長期休暇を取得して、家族や親戚が集まる行事に参加するのが一般的です。仕事後の家族と過ごす時間も重視しており、基本的に残業はおこないません。定時までに業務が終わるよう仕事環境を整えるようにしましょう。 ベトナムが注目される3つのメリット ① 市場の成長性 ベトナムでは、2007年のWTO加盟以降、貿易の自由化が進んでおり、外資に対する各種規制緩和も進んでいます。ベトナムの人口は増加し続けており、国民1人当たりのGDPも成長し続けており、安定した経済成長を続けている点など日系企業にとって魅力となっています。法人税の優遇制度も実施されており、積極的にベトナム進出を後押しする体制ができていることもメリットになっています。また、政治的な安定度も高いことから、投資対象として有望視されています。 ※グラフのデータは『世界銀行』参照 ② 安価な労働力 消費市場としての成長性とともにベトナム進出の主要因として挙げられるのが、人件費の安さです。賃金水準は、物価上昇もあって企業は年々ベースアップをおこなっており、以前よりかなり上がってきているものの、それでも中国やタイ等と比較すると低くなっています。低賃金の国々の中でも比較的インフラが整備されており、多くの日系企業がベトナムに進出しています。 ※グラフのデータは『JETRO(日本貿易振興機構)2022年度 海外進出日系企業実態調査』参照 ③ 優秀な人材 ベトナムは、平均年齢が31歳と若い上に、今後も人口増加が続き、2025年には1億人を突破する見込みとなっています。識字率も95%と非常に高く、勤勉で向上心が強く、新しい知識を貪欲に吸収し、かつ真面目に仕事に取り組みます。政府も外国語・情報技術の強化、教員の質の向上、教育のデジタル化を図っており、国を挙げて教育にも力を入れています。技術力やITリテラシーも高く、質の高い仕事を期待することができます。若くて優秀な人材が多いこともベトナム市場の魅力です。 ※『JETRO(日本貿易振興機構)2021年1月 ベトナム教育(EdTech)産業調査』参考 ベトナム進出のデメリット3つ ① インフラの未整備 ベトナムは、国を挙げてインフラ整備に取り組んでおり、インフラ状況が改善されつつありますが、それでも十分なインフラ整備がなされているとは言いづらい状況です。道路の未整備などで渋滞や事故に巻き込まれるケースもあります。現在、様々な計画が進められてはいますが、資金調達やプロジェクトの管理能力が不十分で、計画通りに進んでいない案件も発生しています。 また、近年の著しい経済発展に伴い、都市部や工業地帯を中心に大気汚染や水質汚染が年々悪化し、健康被害や自然の生態系への影響も出ています。ベトナム政府は環境問題に対する罰則強化をおこなっています。 ② 不透明な法制の運用 ベトナム政府は、国際専門家の意見や提案を取り入れ、法制度の整備に努めています。各種法制の運営についても、管轄当局や処理手続き、受付窓口をおり簡素化、効率化する体制の構築が進んでいます。 しかし、法制度の整備は進んでいるものの、裁判例の蓄積・公開が十分でなく,具体的な指針となるものが不足しており、当局や裁判所の裁量が大きくなっているケースもあります。各省や担当員によって解釈が異なることもしばしばある為、信頼できる第三者からのアドバイスや客観的な判断を仰いだほうがよいでしょう。 ③ 管理職クラスの人材確保が困難 ベトナムは人口ピラミッドにおいて、若年層が多く、労働力は豊富です。一方で、ビジネス経験の豊富な管理職といった人材を確保することは困難となっています。ある日本企業では、日本へ留学するベトナム人が多いことに着目し、日本で技術を学んだ技能実習生や就業経験のあるベトナム人などが帰国した後、ベトナム拠点で採用するといった対策をしています。 現地日系企業の動向 ベトナムには3つの日本商工会議所があり、日本企業の活動支援をしています。この日本商工会議所の会員企業数がベトナムに進出している日系企業数として参考にされることが多く、3つ合わせて約2,000社が登録されています。実際には会員になっていない日系企業もいますので、実態はもっと多く日系企業が進出しているといわれています。 ベトナム北部(ハノイ):ベトナム日本商工会議所 801社 ※2023年2月時点 ベトナム中部(ダナン):ダナン日本商工会議所 210社 ※2022年6月時点 ベトナム南部(ホーチミン):ホーチミン日本商工会議所 1,048社 ※2023年2月時点 2022年度のJETRO(日本貿易振興機構)調査結果によると、今後1~2年の事業展開の方向性で、拡大と回答した日系企業の割合は、インド、バングラデシュに続いて、ベトナムは3番目と高い水準を示しています。 ※グラフのデータは『JETRO(日本貿易振興機構)2022年度 海外進出日系企業実態調査』参照 失敗しないベトナム進出のポイント3つ ① リスク管理 一度失敗してしまうとコストと労力もかかる為、失敗しにくいスキームを構築することは大切です。可能な限りリスクを低減させてから、そのリスクの中で勝負をしていくことが重要です。 進出といっても、様々な進出形態があります。現地に拠点を構える場合は、現地法人設立、M&Aでの現地法人買収、現地パートナーとの合弁、支店設立などがあります。また現地に拠点を設けない場合であっても、輸出取引、販売代理店、フランチャイズ、製造委託、EC活用、ライセンス契約、技術提供(指導)契約など様々です。それぞれの形態ごとに、現地企業との組み方、契約スキームなども異なります。 これだけ多くの選択肢の中から最適なスキームを構築するためには、現地の法律だけでなく、取引の実状や起きがちなリスクを踏まえたリスク管理の視点が不可欠です。 ② 知的財産や営業秘密保護の戦略 海外では、知的財産権の侵害(模倣品)、技術漏えいなど、国内では想定しづらい様々な問題に直面することがあります。安定した収益を上げるためにも、知的財産権のみならず営業秘密管理や、契約スキーム自体の組み方などを通じて、適切に実践しておくことが重要です。 ③ 現地の法規制や商習慣の把握 不明確な現地の法規制、思わぬ労働慣習や商習慣があります。また急に制度が変わったり、その運用に変更が生じたりと、予定していた計画が大幅に狂ってしまうこともありますので、これらの情報を事前に把握した上で計画を立てる必要があります。そのためにも最新の現地法規制や運用、商慣習などの実践的なアドバイスを受けておくことが重要です。 明倫国際法律事務所では、ベトナム(ハノイ・ホーチミン)にも事務所を構えております。日本人弁護士はもちろん日本語ができるベトナム人弁護士、パラリーガルが常駐し、迅速的かつ適切に対応できます。今回、記載した内容のサポートはもちろんのこと、初期の検討段階から実際の設立、その後の運用支援まで、ワンストップで対応しています。また、コンサルティング会社では担うことのできない、発生したトラブルの解決、紛争対応などの対応は、もちろん未然に防ぐための企業戦略のコンサルティングサポートも可能です。「海外進出や販路拡大について広く知りたい」「現地の投資環境について全体像を掴みたい」等のご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

ベトナム国内企業が海外から融資を受ける場合の規制の改定
弁護士 布井 千博 ポイント 2022年9月30日に、企業の海外ローンに関する通達12号12/2022/TT-NHNNが国家銀行から発出され、11月15日に発効しました。この通達は、企業が海外ローンを組むに際しての手続的な面を主に規定しており、ベトナムに進出している日系企業が親会社から借り入れをしている場合に影響をもたらします。特に緊急の対応を要する点は、海外ローンに関する国家銀行へのローン実施報告が、従来の4半期報告から月次報告に変更されたことです。この規定は、すでに実施されている海外ローンにも適用されますので、対象となる企業においては、手続違反とならないよう速やかな対応が必要です。 1 規制の概要 日系企業がベトナムで子会社を設立して事業を行う場合、ベトナムでの事業活動のために資金を調達する必要があります。現地子会社の資金調達方法としては、親会社がベトナム子会社に資本金として出資する場合のほかに、親会社からの借入(親子ローン)が多く利用されています。 この親子ローンの実施には、国境を超えた資金移動が生じることから、日本側並びにベトナム側の双方において外国為替法の規制対象となります。とくにベトナム側では厳格な為替管理が実施されており、日越間の親子ローンについても様々な手続が求められています。90年代後半のアジア通貨危機の教訓などを踏まえて、急激な為替変動を防止するために厳格な為替管理を行っているといえましょう。 さて、そもそもの前提として、ベトナムにおいて国内企業や個人が外国からローンの借入をすることは、法律(外国為替条例06/2013/UBTVQH13。以下、外為条例という。)で明確に認められています。外為条例17条1項は、企業、金融機関、個人などの居住者が、法律規定および自己借入-自己返済の原則に基づき、外国からの借入と対外債務の弁済を行う権利を有するものと定めています。海外からの借入は、資本取引に該当し(外為条例4条4項)、企業、金融機関、個人などの居住者は、ベトナム国家銀行(SBV)の規定に従って、海外からの借入及び返済、借入登録、口座の開設と利用、借入金の出金と返済のための送金、ローン実施の報告などに関する義務を遵守することが求められます(外為条例17条2項)。 この外為条例を施行するため、政令と通達が定められています。政府保証のない企業の海外ローンの借入及び返済の管理に関する2013年政令219号219/2013/ND-CPは、政府が、国家財政の安定とマクロ経済の均衡確保という観点から、企業による自己借入-自己返済の方式による海外借入を管理するものとしています(政令219号4条1項)。海外借入を行う企業には、政府あるいはベトナム国家銀行が定める法規を遵守することが求められ、海外ローンを適切な目的及び業務の範囲内で使用するなど様々な責任が課せられます(政令219号4条2項、14条)。とくに、海外ローンの借主には、国家銀行の規定に基づいて、資本の出金と外債の返済について、定期的または個別に報告する義務が課せられます(政令219号16条1項)。本政令の違反に対しては、行政罰または刑事責任が課せられるものとされています(政令219号17条)。 この政令を受けて、企業による海外ローンの借入と返済に関して二つの通達がベトナム国家銀行から発出されています。第一は、2022年9月30日に発出された通達12号12/2022/TT-NHNNです。この通達は、政府保証のない企業の外海外ローンに関して、海外ローンの登録手続、借主による海外借入口座の開設、借入金の引出と返済のための手続(外貨の購入と送金を含む)、海外ローンに対する担保義務の履行、統計報告など、主として手続的な面の規制を行います。第二は、2014年2月26日に発出された通達12号です。この通達は、企業が海外借入を行う際に従うべき要件を定めるものです。海外ローンは、満期が1年以内の短期海外借入と、満期が1年超の中長期海外借入に区別され(2014年通達12号2条)、短期及び中長期の借入金の使途や借入限度額、海外ローン契約、貸付通貨、海外ローン費用などが定められています。この2014年通達12号については、2022年3月11日にパブリックコメントのために公開草案が発表されていますが、これまでのところ本通達の改正は行われていません。 さて、2022年通達12号(以下、新通達という。)の発出に伴い、2016年通達3号、2016年通達5号、2017年通達5号の三本の通達(以下、旧通達という。)は失効しました。以下、改正点を交えながら、新通達のポイントを説明します。 2 登録手続 海外ローンは、借入期間が1年以内の短期ローンと、借入期間が1年を超える中長期ローンに分類されて規制されます(2014年通達12号2条)。短期ローンは、運転資金等の目的に限られ、設備投資などの中長期資金の目的で借り入れることはできません(2014年通達12号11条1項)。中長期ローンは、運転資金に限らず、設備投資などに用いることができますが、ローン契約を国家銀行に登録することが求められます。 海外ローン契約の国家銀行への登録は次の場合に必要です。まずは、借入期間が1年を超える中長期ローンです(新通達11条1項)。次に、短期ローンであっても、元本返済期間が更新されて償還期間が1年以上となる場合や、返済の遅延により借入金の入金日から1年と30日が経過しても元利が弁済されていない場合にも、中長期ローンとして登録の対象となります(新通達11条2項3項)。なお、返済遅延による短期ローンから中長期ローンへの変更に関する登録義務の発生日については、新通達により変更され、従来の入金日から1年と10日とされていたところを、1年と30日に延長されました。これにより、短期ローンの借主に登録義務が発生するまで多少の猶予が与えられたことになります。 (1)管轄 1,000万米ドル(または相当額、以下同じ)を超えるローン、および、国家銀行総裁の検討・承認対象となるドン建て海外ローンは、国家銀行本店の外国為替管理部門が管轄します。1,000万米ドル(またはその相当額)までの貸付金、および、省の国家銀行総裁の承認を得たベトナムドン建ての海外ローンは、借主の本社が所在する省の国家銀行支店が管轄します。海外ローンに関する登録、変更および報告はそれぞれこの管轄部門・支店に対して行うことになります(新通達20条)。 (2)中長期ローン契約の国家銀行への登録時期 中長期ローン契約を締結した場合、締結日から30日以内に海外ローンの登録申請をおこなわなければなりません。短期ローンを更新して中長期ローンとした場合には、更新契約の調印日から30日以内に、また短期ローンを期限までに返済できず1年を超えた場合には、借入金の入金日から1年が経過した日から60日以内に登録申請をおこなう必要があります。ただし返済期限までに返済できなかった短期ローンについては返済猶予期間(30日)が設けられており、借入期間が実際に1年を超えてしまったとしてもこの返済猶予期間内に返済を行えば登録は不要です(新通達15条2項)。 (3)投資準備資金の海外ローンへの転換 新通達はこのほかに、投資登録証明書IRCの付与されたプロジェクトの投資準備資金を海外ローンに転換する場合について、借主が企業登録証明書または特別法による設立・運営許可証を取得した日、PPP投資契約を締結した日、投資準備資金をローンに転換する海外ローン契約を締結した日(いずれか遅い日)から30営業日以内に申請書を提出するとする規定を新たに導入しました(新通達15条2項c号)。 (4)登録手続 登録はオンラインまたは書面により行うことができます。オンラインを選択する場合、国家銀行のポータルサイト(www.sbv.gov.vn)からローン登録用ウェブサイトへのリンクを開くか、登録用ウェブサイト(www.qlnh-sbv.cic.org.vn)を直接訪問し、事前に貸付情報の登録を行った上で、実際のローン登録手続を行うことになります(新通達5条、15条1項a号)。オンライン登録では、登録用ウェブサイトの指示にしたがい必要な情報を入力後、データをプリントアウトして代表者サインと押印をした書類およびウェブサイト上で指定された証明書類をオンラインで提出するか、管轄当局の窓口に直接提出または郵送します。 書面での登録をする場合には、新通達12号付録1の様式に基づいた申請書に必要事項を記入し、これに所定の証明書類を添付して当局の窓口に直接持参または郵送により提出します。 提出書類の主なものは、①申請用紙(オンラインの場合はウェブ上の申請フォーム、書面提出の場合は新通達12号付録1の様式)、②借り手である現地法人側の地位を証明する投資登録証明証(IRC)および企業登録証明証(ERC)等のコピー、③借入金の使途説明書類(事業計画や生産計画等)、④ローン契約書のコピーおよびベトナム語訳、⑤担保・保証がある場合は担保・保証書のコピーとベトナム語訳等があげられます(新通達16条)。 新通達は、投資プロジェクト実行のための融資について、投資登録証明書または投資方針承認決定書の提出を求める規定を新たに導入しました(新通達16条3項a号)。借入目的の判断材料として投資登録証明書などが用いられると、従来提出が求められていた借主の作成した生産・事業計画よりも借入目的が狭く解釈される恐れがあります。これにより、海外ローンの使途が制限されることが懸念されます。また、登録するローンの具体的な内容や管轄窓口によって追加書類が必要な場合もあるため、法令の定めをよく理解した上で、事前に当局に対して具体的な確認を行うことが不可欠となります。 (5)登録手続所要期間 新規登録に要する期間については、国家銀行からの登録可否の回答は、オンライン登録の場合は原則として12営業日以内、書面提出の場合は15営業日以内に出されます。ベトナムドン建の中長期ローンについては回答の受領まで最大45営業日かかります(新通達15条3項)。回答の結果次第では、ローン契約を変更して改めて登録申請をしなければならないこともありうるため、登録完了までに想定外の時間を要する可能性があります。他方で、登録が承認されたにもかかわらず出金期間の最終日から6ヵ月を超えて借入金の出入金が実行されない場合には、登録が自動に失効します(新通達23条1項)。このようなことから、現実の資金需要を勘案して、時間的に余裕をもって登録申請に臨むことが必要です。 3 変更登録 すでに登録された中長期ローンの内容に何らかの変更が生じた場合は、変更内容に応じて国家銀行に対し変更登録または通知を行わなければなりません(新通達17条1項)。基本的に、ローンの内容の重大な変更については変更登録が求められ、軽微な変更についてはWEB上で国家銀行に変更内容を通知するだけで足り、変更登録を要しません。例えば、当初計画と比べ10営業日以内の借入金の出入金時期あるいは返済時期の変更、同一県・市内における住所変更、利息及び手数料の計算方法の変更を伴わない利息及び手数料の支払計画の変更、少額の借入金の出金または元利返済などは、変更登録を免除され通知だけで足ります(新通達17条2項)。 なお、新通達は会社分割や合併により海外ローンが包括承継された場合についての規定を新たに導入しました(新通達6条)。新通達は、会社分割及び合併による承継人が、海外ローンに関する権利義務を引き受け、借主の責任を履行すべきであると規定しており、海外ローンが登録されている場合には、上記M&Aによる海外ローンの変更に関して変更登録を行う必要があると考えられます。 4 ローン実施報告 借主は、毎月、報告期間の翌月5日までに、国家銀行が設けるウェブサイト上(新通達8条)で、短期、中期および長期のローンに関するオンライン実施報告を作成しなければなりません(新通達5条2項、41条1項)。旧通達の下では、このローン実施報告は四半期に1度とされていましたが、新通達により月次に変更されました。また、このオンライン報告は、国家銀行への登録が必要な中長期ローンだけではなく短期ローンについても義務とされている点に留意が必要です。なお、Webサイト上の技術的な障害によりオンライン報告ができない場合には、書面での報告が必要となります(新通達41条1項)。 国家銀行は、借主からのインターネット報告の受領後10営業日以内にデータベースへの保存を行い、電子メールで報告完了を借主に通知するものとされています(新通達41条2項)。報告に修正が必要な場合には、国家銀行支店は、借主に通知メールを発信し、借主はオンライン上でデータの修正を行います(新通達41条3項)。 報告義務の違反に関しては、金融および銀行部門における行政違反に対する罰則に関する2019年政令88号が適用されます。同政令47条によれば、報告義務の遅延などの軽微な違反に対しては、500万ドンから1000万ドンの罰金が科せられます(同政令47条1項)。報告を提出しないか、報告内容が不十分な場合には、1000万ドンから1500万ドンの罰金が科せられます(同条2項)。 5 今後の留意点 海外ローンの管理を強化するという国家銀行の意図は、海外ローン実施報告の期間を四半期から月次に変更した点からも窺うことができます。ただし、新通達の対象は主として海外ローンに関する手続規制に限られることから、国家銀行が描く規制強化の全貌を評価するには十分でありません。現在進められている2014年通達12号の改正が成立すれば、企業による海外ローンの新たな認可要件が明確化されます。今後の通達制定の状況に留意が必要です。 以上

ベトナムにおける労働者の試用規制
弁護士:原 智輝 1.試用期間の設定 試用期間は、適切な人材確保段として機能を有し、ベトナム労働法第24条1項にて、採用にあたり、雇用者と被雇用者は、試用について合意することができる旨定めが置かれています。通常は、自由に試用期間の有無を設定できますが、雇用期間が1か月に満たない場合、試用期間を置くことができません(同条3項)。試用期間は雇用契約と共に又は別の契約として定めることができ、試用期間を単独の契約とする場合、以下のような内容が必要となります。 ① 使用者の名称、住所及び使用者側で労働契約を締結した者の氏名・職位 ② 労働者側で労働契約を締結した者の氏名・生年月日・性別・居住地・市民カード若しくは人民証明書又はパスポートの番号 ③ 業務及び職場の住所 ④ 試用期間 ⑤ 業務又は職位に沿った賃金額、賃金の支払方法、賃金支払時期、手当及びその他の補充項目 ⑥ 労働時間、休憩時間 ⑦ 労働者に対する労働保護設備 上記項目の他、契約自由の範囲内で様々定めることが可能です。注意点として、労働法第25条によれば、試用期間は、業種や業務内容に応じて上限が設定されています。 ① 企業法、企業における生産・経営に対して投資する国家資本の管理・使用の法律に従った企業の管理者の業務については、180日。企業法第4条24号によれば、企業の管理者とは、私人企業主、合名社員、社員総会の会長、社員総会の構成員、会社の会長、取締役会の会長、取締役、社長又は総社長及び会社定款の規定に従ったその他の管理職の地位にある個人からなる私人企業の管理者及び会社の管理者をいうとされています。 ② 短期大学以上の専門・技術水準を必要とする業務については 、60日。ここでいう「短期大学以上の専門・技術水準を必要とする」かどうかは、使用者側の判断に一次的には委ねられています。一定の公務員や准公務の専門・技術水準については法規範文書(基本的には各省庁の通達)が参考になりますが(例えば、教育訓練省の通達04/2021/TT-BGDĐTによれば、高校の教師は学士号(大学卒)以上を要するなど)、このような参考基準がある業種は多くはありません。 ③ 中級の専門・技術水準を必要とする職位の業務・技術工員・事務職員については 、30日。この業種についても「中級の専門・技術水準を必要とする」かどうかは、使用者の判断が一次的なものとして行われる余地が大きいとされています。 ④ その他の業務の場合は6日。特に資格等を要しない単純業務(例えば、家政婦やごみ収集・道路掃除作業員など)が例として挙げられます。 この、試用期間ですが、特定の業務1つに対してそれぞれ設定できるとされています。しかし、そうすると、業務を細分化することで、複数回に渡り試用期間を設定することができ、容易に労働者に試用条件下での長期雇用を強いることが可能になるため、そのような方向性で試用期間を用いることは慎んだ方がいいと思われます。 2.試用期間中の給与や保険 試用中の労働者の賃金は、試用期間終了後におけるそれの85%が必要です(労働法第26条)。 試用期間中における保険加入の要否は、試用期間が雇用契約と一体とされている場合とそれぞれ独立している場合とで異なると考える余地があります。社会保険法2条1項では、雇用契約が加入条件となっているため、一体型の場合には加入を要するが、独立型の場合には必須ではないと解釈する余地があるためです。実際上、試用契約を独立させている場合において、試用期間中に社会保険に加入している例は少なく、このような解釈で実務が運用されていると推察されます。 3.試用の終了 使用の終了条件は、 i)試用期間の満了 ii)試用終了の通知を当事者のいずれかが行ったとき とされています。 試用期間の満了に伴って、使用者は労働者に対して、通知を出さなければならず、試用の目的である、業務水準に達していたか否かを通知しなければなりません。水準に達していた場合は、一体型、独立型いずれにおいても雇用契約に移行し、達していない場合は契約終了原因となります(労働法27条)。いったん雇用契約関係が形成された場合にその終了を使用者側から導くのが困難なベトナム労働法の規律において、この試用期間においては、労働者は特段手続を要することなく、また、損害賠償義務を負うことなく、契約を終了させることができるので、試用期間中においては労働者の見極めが重要と言えそうです。

ベトナムにおけるバイク・ツーリズムと問題点
弁護士:布井 千博 ベトナムでは、バイクは庶民の足としてだけではなく、今や外国人旅行客にとっても重要な移動手段として用いられています。とくに個人旅行の場合は観光地での交通の便が悪いため、レンタルバイクをすることが一般的に行われています。バイクのレンタル料も手ごろで、1日5ドルほどから借りられます。また、最近注目されているベトナム北部の観光地ハザン(Ha Giang)などは、全行程4日間で山岳地帯をレンタルバイクで踏破するという周遊プランが好評で、とくに欧米の若者に人気があります。 ここで皆さんは、ベトナムでバイクを借りるのには免許がいらないのか疑問に思われるかもしれません。まず、ベトナムでは排気量50ccまでのバイクについては免許が不要です。ただし、レンタルショップで借りるバイクの多くは排気量100cc前後のバイクです。この場合、当然のことながらベトナムの道路交通法上、バイクの免許(排気量175ccまでのバイクに乗れるA1ライセンス)が必要です。無免許運転は当然のことながら禁止されます(2008年道路交通法)。 自国において二輪免許を持っている場合でも、ベトナムでは、日本の国際免許証や免許証は通用しません。国際免許については、ベトナムが加盟する道路交通に関するウィーン条約が、日本が加盟するジュネーブ条約と異なるため、ベトナムでは日本で発行された国際運転免許証が有効でないのです。また、外国免許からベトナム免許への切替えには、ベトナムの滞在許可証や長期滞在ビザが求められるため(2017年通達12号)、免許の書き換えは通常の旅行者には困難です。日本人旅行者に限らず、外国人旅行者がバイクを運転する際には無免許であることがめずらしくありません。 ベトナムでは、無免許運転に対する制裁は日本と比べて軽微です。175ccまでのバイクについての無免許の罰金は、最近の改正で引き上げられたとはいえ、100万ドンから200万ドン(米ドル換算で約50~100ドル相当)です(2021年政令123号21条)。また、日本のように無免許だけで懲役刑が課せられることはありません。ただし、重大事故を起こしかつ無免許であった場合には、3年以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法260条2項)。これ以外に注意すべき点は、交通違反を摘発した警察に違反者のバイクを没収する権限が認められていることです。バイクを没収されると、罰金の決定が行われまでバイクを返してもらえません(政令123号82条)。無免許でレンタルバイクを運転する場合、没収のリスクを抱えることになります。 ところで、ベトナムでは交通警察に汚職が蔓延しており、無免許で捕まってもワイロを渡せば放免されることが常識となっています。ワイロの額は、それこそケースバイケースですが、外国人の場合には50万ドンから100万ドン程度ともいわれています。レンタルバイクで警察に捕まった場合、バイクの没収というリスクもあるため、ワイロを支払わざるを得ない状況です。当然のことですが賄賂の支払いは刑事罰の対象で、200万ドン以上の賄賂を渡せば、理論上ではありますが、6月以上3年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法364条1項)。 これ以外にも無免許での事故には保険金の支払いが認められないなど、無免許運転には様々なリスクが伴います。ベトナムは、俗化がそれほど進んでいない観光地が数多く残されています。街角の旅行会社では日帰りや短期のバス旅行が数多く販売されています。皆様には無免許運転のリスクを冒さず、ベトナム旅行を楽しんでいただければと思います。

現地法人の所在地移転時の注意点
弁護士:原智輝 パラリーガル:Hanh Le 会社本店の移転など所在地が変更される場合、所在地と関係がある設立証明書、各ライセンス、その他会社書類の修正を考える必要があります。原則として、ある書類に記載される情報を変更すると、その書類の変更手続を行う必要があります。 • 現地法人設立に関する証明書 √ IRC(投資登録証明書): IRC変更手続 √ ERC(企業登録証明書): ERC変更手続 • 印鑑 社印が住所表記を含んでいる場合、社印の変更手続も必要です。現行の投資法・企業法に基づき設立した企業では、公的手続を経ずに社印を更新できますが、他の企業(例えば:外国商人の支店、外国商人の駐在員事務所、法律事務所等)は公安省・公安局で社印変更を登録する必要があります。 • 税務機関への通知 税務局は外資系企業を管理している関係上、同一県内で住所を変更する場合、担当機関は変更されず、税務機関への通知のみが必要となります。実務運用上は通常ERC変更手続をポータルで行う際に税務機関へ通知できます。 一方、県をまたぐ移転の場合、税務担当機関を変更する必要があるため、より複雑な手続となります。上記の税務機関への通知手続の他、現地法人に関する証明書変更前に税務担当機関にて会社の税務義務の確認手続を行うことが必要です。新ERCを取得した後、税務機関への通知手続を行います。 • 社会保険への通知 会社住所の変更は労働者の勤務場所及び労働者の社会保険に関するので、社会保険機関に通知する必要があります。同一県内で住所を変更する場合は、社会保険担当機関は変更されないため、通知手続の必要はありません。 一方、県をまたぐ移転の場合、社会保険担当機関を変更する必要があるため、通知手続が必要になります。現地法人に関する証明書変更前に旧担当機関で社会保険停止手続をし、新ERCを取得後に新担当機関で社会保険の登録手続が必要です。 • インボイスに記載される住所の変更:税務機関への通知手続のみではインボイスのアプリケーションと連動していないためインボイス アプリケーション上で住所変更する必要があります。 • 外国人の労働許可証:労働者の勤務場所に関係があるため更新が必要となります。 • 銀行への通知:法令上の要請ではありませんが、通常は所在地変更の届け出が必要となります。 上記の各手続を行わない場合、以下のようなリスクがあります。 • 現地法人設立に関する証明書の場合:IRC又はERC変更を行わない場合の罰則。 – IRC:70,000,000 VND から100,000,000 VNDの罰金及び変更手続(政令No. 122/2021/ND-CP第 17 条2 項 b号) – ERC:20,000,000 VND から30,000,000 VNDの罰金及び変更手続(政令 122/2021/ND-CP第 44 条5項) • 税務、インボイス、社会保険について: 税務局からの納税書その他の税務に関する通知書が全て旧住所に転送されるため、会社は当該文書を受領できず、税務局との応答に支障が生じます(社会保険機関も同様)。また、税務局が検査を行う場合、企業登録証明書に記載されている所在地で検査を行うため、変更届出がなされていないことが発覚し、罰金が科される場合があります。最悪の場合、税務局はその会社の税コードを閉鎖でき、事業登録証明書を回収するように計画投資局に通知する場合があります。(通達105/2020/TT-BTC第17条参考) • 外国人の労働許可証:外国人労働許可証の内容と一致しない外国人労働者を雇用した場合、各従業員に5,000,000 VNDから 10,000,000 VNDまでの罰金が科せられます。(政令 28/2020/ND-CP第 31条2項)

債権管理読本 ~第1回 取引債権と紛争解決コスト比較について~
弁護士 原智輝 ベトナム債権管理チーム(パラリーガル Giang、Hanh) ベトナム現地法人の取引やベトナム企業との貿易取引など、ベトナムに関連する債権が発生する取引は日々多々生じています。外国企業との取引においては、日本国内企業同士の取引とは異なった視点からの債権管理が生じます。弊所へのご相談の中でも近時、ベトナム企業に対する債権回収案件が増加傾向にあり、その重要性は高まっていると言えるでしょう。 各種相談を経て思うのが、日系企業における債権管理の第1歩は、発生させている債権(額)の意味に関する知識を深めるというところだろうと思います。訴訟や仲裁など、債権回収の場面になった際、一体いくらの費用が見込まれるのかを知ることで、今発生させている債権に対する認識やリスクを察知できるからです。そのような理由から、まずは紛争解決方法に焦点を当てて話を進めていきたいと思います。 債権回収の相談の際、最終的な解決は、日本又はベトナムでの裁判所での訴訟手続か仲裁手続による仲裁判断となります。この選択は事実上、取引開始時における契約書の記載等によって決定するものであり、この時点で誤った選択を行った場合、泣き寝入りをせざるを得ない状況に追い込まれたり、手続は採れるものの費用倒れになったりしてしまいます。そのため、債権回収を見越したタブーについて記載し、どのような視点で手続選択を行えばいいのか考えてみたいと思います。 まず、決してやってはならないことは、執行のできない裁判所を用いての紛争解決です。例としては、日本国内にベトナム企業の財産が存在しない状態で、日本の裁判所を専属的合意管轄に指定する場合があります。これは、日本とベトナムの裁判所間において他国の裁判判決を自国で執行する制度になっていないことから起因しており、日本の裁判所で勝訴判決を得たとしても、ベトナムで執行ができず、判決が「絵に描いた餅」となってしまう形となって現れます。もし、自社の取引契約書を確認し、日本の裁判所が専属的合意管轄となっている場合や、紛争解決に関する記載が何もない場合はかなり要注意と言えるでしょう。 次に、仲裁手続利用の可能性についてです。仲裁判断において主に生じる費用は、管理料金、仲裁人報償金及び代理人への着手金と報酬金などが挙げられます。前2者が仲裁機関に支払う費用、後2者が代理人となる弁護士に支払う費用になります。仮に、1000万円の請求をJCAA(日本商事仲裁協会)の商事仲裁規則を用い、仲裁人の人数を1名とした場合、管理料金が50万円、仲裁人報償金の上限が200万円(1時間5万円のタイムチャージ)(仲裁人報償金については両当事者に予納金の請求が生じます)、弁護士着手金が59万円、全額回収時の報酬金が118万円(弁護士費用についてはいずれも旧日弁連弁護士報酬基準を参照)となります。なお、JCAAの商事仲裁規則80条によりこれら費用負担割合については、仲裁判断に従って各当事者の分担となるため、全額の費用負担が必要となるケースは稀であろうかと思われますが、目安として、このような事情から債権が数百万円程度にとどまる場合、各種費用の関係から厳しい判断を迫られる可能性があることを認識する必要があります。 まとめますと、自社取引において発生させている売掛債権が例えば100万円~200万円程度である場合や、相手方の契約違反により生じる自社の損害が同額程度である場合、その金額から、債権管理上何らかの措置を講じなければ、泣き寝入りか費用倒れのリスクをもって取引を続けている可能性が高いということになりそうです。なお、この売掛債権は、基本的には、1社に対する請求であり、契約書の関係性によっては、債権に紐づけられた契約書単位で考える必要があります。 次回は、引き続き、ベトナム裁判所における訴訟費用や、VIAC(ベトナム仲裁機関)における費用について説明していきたいと思います。

ベトナムの付加価値税(VAT)に関する改正案について
ホーチミン支店代表弁護士 盛一也 パラリーガル Truong Vu Giang ベトナムの付加価値税(VAT)について、新たな内容等を設けた政令No.15/2022 NĐ-CP(政令15)が施行された後、多くの企業が、減税の対象となる商品やサービスのインボイスの作成について困難に陥っている。そのような困難を解消するために、2022年3月30日に財務省が、政令15の第1条4項の改正政令草案を政府に提案した。 現行政令15の1条4項の規定は、以下の通りである: 「事業は、付加価値税(VAT)の減税の対象となる商品・サービスに対して、個別のインボイスを作成しなければならない。 事業が付加価値税減税の対象となる商品・サービスに対して別途インボイスを発行しない場合、付加価値税の減税を受けることができない。」 すなわち、減税の対象である商品・サービスを提供しても、当然減税を受けられるわけではない。言い換えれば、8%税率が適用されるためには、企業は、8%税率が適用されるものについて特定したうえで、インボイスを作成しなければならない。 付加価値税の減税は、本来であれば、需要を喚起するためのもので、企業の新型コロナによる影響後の事業活動をサポートする目的がある。ただし、政令15の上記の規定により、逆に企業の支出費用が増加する可能性があると多くの企業が主張している。具体的には、会計処理時間の費用とインボイスの印刷・使用費用である。…

問題従業員に対するベトナム労働法上の対処法
問題従業員に対する対処法は、ベトナム労働法(No.45/2019/QH14)に基づき、以下の図式のとおり、大別して労働契約関係を終了させる方法と労働契約関係を終了させない方法がある。 1.解約権行使 使用者の解約権行使が可能となるのは次の場合である(法36条)。 (1)労働者が業務を常時完成させない場合 (2)労働者が病気や事故で長期に治療を受けたが労働能力を回復しない場合 (3)不可抗力の理由により事業縮小する場合 (4)労働契約の一時的履行停止期間満期日から15日以内に労働者が職場に復帰しない場合 (5)労働者が定年退職年齢となった場合 (6)労働者が5日以上連続で正当な理由なく仕事をしない場合 (7)労働者が誠実な情報を提供せず労働者の採用に影響を与える場合 これらの中で(4)と(6)においては、使用者は事前通知を行う必要なく解除権を行使することができる。 他方で、使用者は、労働者が疾病等の治療中である場合(上記(2)の場合を除く)、正当な理由で休暇を用いている場合、妊娠中、産休中又は生後12か月未満の子供を養育している場合は解除権が制限される。 2. 労働規律処分 使用者は、労働規律を違反した労働者に対して、上記の対処法一覧図のとおり、労働契約関係終了に至る解雇処分又は労働契約関係終了に至らないけん責処分若しくは6 か月を超えない昇給期間の延長若しくは免職を適用することも可能となる。 これらの中で、最も厳重な処分である解雇処分は、法125条で定める次の場合に可能となる。 (1)労働者が職場で、窃盗、横領、賭博、故意に基づく傷害の惹起、麻薬使用をする場合 (2)労働者が、営業機密、技術機密の漏洩、知的所有権の侵害行為を行う、若しくは使用者の財産、利益に関して重大な損害を惹起する行為を行う、若しくは特別に重大な損害惹起のおそれがある行為を行う、若しくは職場でのセクシャルハラスメントを行う場合 (3)昇給期間の延長又は免職の規律処分を受けた労働者が、規律処分が解消されない期間内に再犯をする場合 (4)労働者が、正当な理由なく30 日間に合計5日、又は365日間に合計20日、仕事を放棄した場合 他の処分対象行為について、同法は詳細を定めておらず、各社の就業規則の規定にこれを委ねている。そのため、解雇事由を具体化するという点で就業規則には重要な役割がある。 労働規律処分の原則について、一つの労働規律違反行為に対して複数の労働規律違反処分を適用することはできず、一人の労働者が同時に複数の労働規律違反行為をした場合,最も重い違反行為に相当する最も高度な規律形式のみを適用することに注意する必要がある(法122条)。同条によると、労働規律処分を適用するために、使用者は労働者の過失を証明しなければならない。そして、労働規律処分過程においては労働組合の出席が必須である。また、労働者は出席しなければならず、自ら弁護し、弁護士又は労働者代表組織に依頼して弁護する権利を有する。そして、労働規律処分は、議事録に記載されなくてはならない。 法122条4項及び5項によれば、労働者が以下に該当する場合、懲戒処分をできないとしている。 (1)病気・治療静養休暇中、使用者の同意を得た休暇中の場合 (2)逮捕、拘留中の場合 (3)解雇の対象になる(1)又は(2)の行為について、捜査中である場合 (4)妊娠中、産休中又は12か月未満の子を養育する場合 (5)自らの行為認識可能性・行為制御可能性が欠如する疾患をもつ労働者が労働規律違反をした場合 3. 業務異動 原則として、使用者は、1年間で合計60日を超えない日数にて労働者を一時的に異動させることができる。労働者をこの期間を超えて異動させることができるのは、労働者が書面で合意した場合のみとされる(法29 条1項)。 また、使用者は、異動から少なくとも3営業日前にその旨を労働者に知らせなければならない。異動時における賃金に関して、労働契約と異なった業務に異動する労働者は新たな業務に従って給与を受ける旨定められるが、従来の業務と比して新たな業務の給与が低い場合は、30営業日間は従来の業務の賃金が維持される。また、新たな業務の賃金は、少なくとも従来の業務の85%を満たしていなければならず、最低賃金を下 回ることはできない。 執筆者:弁護士 原智輝 パラリーガル Mai Lê

ベトナムにおける産休中従業員の早期職場復帰について
2019年労働法(労働法)139条及び2014年社会保険法(社会保険法)34条によれば、女性従業員は、出産前後6か月の出産休暇を取得する権利があり、出産前の休暇は2か月を超えないとされている。女性従業員が双子以上を出産した場合は、2人目以上の子供1人につき、1か月の休暇が追加される。 上記の法定産休期間前に早期復帰したい場合、雇用者及び従業員は、労働法139条4項及び社会保険法40条に規定された以下の条件を満たさなければならない。 ①産休開始から少なくとも4か月が経過したこと ②女性従業員が事前に雇用者に通知し、雇用者がそれを同意したこと ③権限を有する医療機関が、早期復帰となる女性従業員の健康に害を及ぼさないことを確認したこと 社会保険法39条1項によれば、法定産休期間中、女性従業員の社会保険機関から受け取る給付月額は、産休前社会保険料算出給与の6ヶ月分を平均した額の100%となる。 女性従業員は早期復帰期間中、雇用者が支払った給与に加え、社会保険に従い、社会保険機関からの出産給付を引き続き受けることができる(労働法139条4項及び社会保険法40条2項)。ただし、早期復帰時点から、従業員と雇用者は、従業員のため、社会保険と健康保険を納付する必要がある(社会保険法を案内する通達59/2015/TT-BLĐTBXH)。 上記の社会保険と出産休暇制度は、ベトナム人と外国人従業員に対し、両方とも適用される。 しかしながら、法定の最低産休期間4か月より前に復帰することを目的として業務委託契約を締結することで、労働法の規律を適用しない法形式が選択される場合がある。この場合、両当事者の合意があったとしても、労働法上ではあるものの、母体と胎児双方の保護に出ていることが、早期復帰の条件として、母親の同意だけでなく、医学的に支障が生じていないことが確認されていることから伺われる。そうすると、単純に母体となる母親のみが業務委託に同意したとしても(労働法の適用を排除しようとしたとしても)、胎児の安全が確保されない以上、同法の考え方から違法の可能性が考えられる。 なお、類似例として、正規雇用ではなくいわゆるパートタイムでの早期復帰を検討する場合も見受けられるが、パートタイムの場合は労働法の規律下にあり、上記法令の関係から、産休開始後4か月を経過しない間での復帰は認められない点にも注意が必要である。 執筆者:弁護士 原智輝 パラリーガル Truong Vu Giang

新型コロナからの経済回復策としての付加価値税の減税措置について
付加価値税が2022年2月1日から、10%から8%に引き下げられました。 各企業は、新しい税率の適用が不明確として困難に直面しています。 社会経済の回復と発展のプログラムを支援する金融政策に関する国会の議決第43/2022/QH15号を展開するため、1月28日付の政令第 15/2022/ND-CP(以下、「政令15号」という。)が、免税・減税政策をより明確に規定しました。政令15号の主要な内容は、2022年に付加価値税率を2%引き下げた点です。この減税は、標準税率10%が課されている商品やサービスに適用され、2022年2月1日から、2022年12月31日まで有効となります。 付加価値税(以下、「VAT」という。)とは、事業者が事業の過程で創出する付加価値に課される税金であり、日本の消費税と概ね同様の概念です。事業者は、課税対象となる商品及びサービスの販売時に顧客からVATを徴収し、購入時にVATを支払う必要があります。 ただし、政府はすべての商品及びサービスに対しVATを8%に一律に削減するのではなく、電気通信、情報技術、金融・銀行、証券、保険、不動産事業、化学・化学製品の生産事業、物品税が対象する商品・サービス等の商品・サービスには適用しないものとしました。政令15号の3つの付録にある除外リストによって、それらが明記されています。そのため、減税対象とならない製品・サービスは、10%の税率を維持する必要があります。 政令15号が有効となった約半月後、企業の担当者や税務・会計専門家へのインタビューによると、多くの企業がこの新しい税率を適用するのに困難に直面しているとのことです。 まず、多くの企業は、自社の事業項目がVAT減税の除外リストに含まれているかどうかを明確に把握することが困難です。例えば、政令15号の減税除外リストには、サービス業なら、事業コード、商品なら、輸入段階に必要となるHSコードが記載されています。しかし、各企業は、自社の原料、製品のHSコード又は事業コードを検索することが難しい又はまだ慣れておらず、自社の取り扱う物がどれにあたるか不明確であると主張しています。 次に、製造企業の投入材料と産出製品にVAT税率を適用することに関して、誤解を招きやすいいくつかのケースがあります。政令15号によると、減税は輸入、生産、加工、販売の各段階で一律に適用されると規定されます。その規定から解釈すると、各類の原料の中で、VAT減税が適用されない原料があるものの、生産された製品がVAT減税除外リストに含まれていないなら、その製品は、VAT減税対象となるか解釈が分かれているのです。 例えば、印刷、コピーの業者で、インクは減税の対象ではないですが、用紙は、8%に減税されるなら、印刷完成品は、減税されるかということが問題になってます。 又は、ビール、ワイン等、製品として販売される場合は、10%の税率が維持されますが、飲食店で料理と一緒に提供される場合は、飲食店がどのようにVATインボイスを発行すればいいのか明らかでありません。 それに加えて、政令15の4条によれば、VAT減税が適用される製品・サービスに別途のインボイスを発行する必要があります。別途インボイスを発行しなければ、VAT減税されないとなっています。したがって、2つの製品しか販売しない場合であっても、2つのインボイスが必要となる可能性があるような困難もあります。例えば、政令15号により、ワインは減税対象外の製品ですから、コンビニ等で、顧客にお菓子とワインそれぞれ1つを売るときに、以前は一つのインボイスのみ作成すれば良いですが、政令15号の有効日から、お菓子1個とワイン1本の2つのインボイスに分けて、発行する必要があるかという疑問も呈されています。その場合、会計担当者の作業負担も重くなることが予想されます。 税務当局は、この半月の困難を解決するため、政令15号を案内する通達を発行する予定ですが、案内通達を待っている間、減税条件や減税の対象となる製品を確定することが難しい場合、誤った適用を避けるため、企業は、管理税務当局又は会計・税務専門家に確認しながら実務を運用することが適当といえます。 盛 一也 Truong Vu Giang

【必見】第2回 ベトナム個人情報保護法 ~個人データ保護措置~
はじめに 現在ベトナムでは、個人情報保護法の制定作業が進められています。現在その草案が公表されており、この度、弊所にて草案の翻訳文を公表することとなりました。 第2回では個人データを取得した後の話となる、個人データの取扱方法や取得した個人データにどのような措置が必要となるかという点について解説します。 一般的に必要とされる技術措置 取得した個人データに対して講ずべき技術的措置については、概ね日本で行っている措置とそうは異ならないように見受けられます。基本的には、不正アクセスや漏洩防止を中止とした措置であり、個人データ移転処理を施す場合にトラッキング可能な措置を講じることなどが挙げられています(草案17条)。 個人データの域外移転 日系企業であれば是非とも知っておきたい個人情報の域外移転については、日本と仕組みが異なるため注意が必要です。特筆すべきは、個人データの域外移転には政府承認が必要とされている点です(草案21条1項d)。これは、通常の個人データであっても、センシティブ情報であっても異なるものではありません。また、移転先にてベトナムが求める個人情報保護水準が保たれていることを示す証明書が予定されており、日本の場合、都度この証明書の取得が必要となるのか、日本への移転の場合は当該書面の提出が免除されるのか今後の運用を中止する必要があります。 なお、日本でも個人情報保護法24条により、外国に個人情報保護法を移転させる場合、認定国であれば、同条が定める同意などが不要となりますが、ベトナムはこの認定国に含まれていません。今後、相互に認定国となる場合はデータ移転が幾分か円滑になると見込まれます。 また、個人データを移転させた場合、当該個人データを3年間、ベトナムにて履歴保存する必要があります。データ移転に関する保存情報は毎年、個人情報保護委員会による監査が入ります。ここで、個人情報保護法への対応ミスがあれば、当局とのやり取りが生じますし、罰則の適用を受けるリスクがあります。 このようなことからも、保存内容には草案21条4項が定める所定の項目を含める必要があるため、これら項目はチェックしておく必要があるでしょう。 なお、政府承認手続に要する日数は申請から20営業日が予定されていますが、運用上もう少し後ろ倒しになる可能性も否定できず、余裕をもった申請が望ましいといえます。 制定法令に適切に対応するために 弊所では、この度の個人情報保護法に対応するためのパッケージサービスを提供しております。現地法人で用いることができる日越語のプライバシーポリシー(個人情報規程)モデル案のご提供や、制定個人情報保護法に関するコメント、注意点や制定法対応のために企業が行うべきことのリーガルコンサルティング、草案のバージョンアップや法令が制定された場合のアフターフォローなどが含まれるサービスとなります。 もちろん、現在日本で用いているプライバシーポリシーのローカライズやベトナム語への翻訳、従業員などに対する説明会の実施なども提供しております。 本法令対応が重要であることは分かったけれども、自社の負担をできるだけ軽減したいと思ってらっしゃる企業様におかれましてはお気軽にご相談いただけますと幸いです。 第3章 個人データ保護措置 第17条 技術措置 1.個人データ処理者は、次に掲げる目的で個人データを保護するための管理、技術的及び及び物理的手段を講じなければならない。 a)個人データの機密性、完全性、可用性への確保 b)匿名化及び暗号化 c)個人データ処理者の個人データ取扱履歴の保存、コピー、抽出、保護 2.個人データ処理者は、個人データを取り扱う場合、次の対策を講じらなければならない。 a)個人データの処理に使用される設備への不正アクセスの防止 b)個人データの不正な読取り、コピー、変更、削除の防止 c)個人データが記録、変更、削除又はアクセスされた場合における、その主体、 時点、方法の統計 d)許可された者の個人データへのアプローチ、アクセス、処理の正当な権利の保護 đ)次の内容に応じた個人データの送信、共有及び移転に関する詳細な統計:時間、主体、データタイプ及び保存形式 e)データ通信装置又はデータ記憶媒体を通じて個人データを移転、共有する際には、不正な読み取り、コピー、変更、削除又は破壊は実行されないことの確約 g)次の項目含む個人データ処理設備及びソフトウェアに関する統計:設備の名称・種類及びメーカーの場所・名前;ソフトウェアメーカーの名称、バージョン、メーカーの名称及び連絡先の詳細 第18条 個人データ保護の規定の作成 1.個人データ処理者は、本政令の規定に従い、本政令の内容の実施を明記した個人データ保護に関する文書を作成し、発行するものとする。 2.個人データ処理者は、個人情報を保護する機能を有する部門を設置し、個人データ保護を担当する役員を任命し、個人データ保護委員会とデータ保護を担当する部門及び個人に関する情報交換を行う。 3.個人データ処理者は、個人データの保護に関する問い合わせに対応するための措置を講じなければならない。 第19条 個人データ保護活動の査察及び検査 1.個人データ保護委員会は、公安省のサイバーセキュリティ及びハイテク犯罪防止及び管理部門の局長に、当局の権限における個人データ保護活動の査察及び検査に関する決定を下すよう要請する責任を負う。査察及び検査のチームのメンバーには、個人データ保護委員会のメンバーと管轄当局のメンバーが含まれる。 2.機関、組織又は個人が、個人データの保護に関する規制に違反していると判断する理由がある場合を除き、個人情データ保護の査察及び検査は、1つの機関又は組織に対して年に2回以内に実施されるものとする。 第20条 センシティブな個人データ取り扱いの登録 1.センシティブ個人データは、取扱前に個人データ保護委員会に登録する必要がある。 2.センシティブ個人データを処理するための登録するための書類、手続。 a)次の情報を含むセンシティブ個人データを処理するためのアプリケーション:個人データ処理者の名前、レジストリ又は個人識別コード、事業所、居住地及びその他の連絡先情報;個人データの処理の法的根拠の引用;個人データの取扱目的;個人データの種類;データが処理される対象の種類;個人データソース;個人データの送信を許可された個人又はグループ;個人データを海外に移転するための条件;個人データ保護対策の詳細な説明。 b)次の項目を含む、センシティブな個人データを処理する際の影響評価報告書:提案された取扱活動、取扱の目的及び取り扱っている個人データの性質;提案された取扱活動のある個人データ主体に発生する可能性がある潜在的な危害の評価;当該危害リスクを管理、軽減又は排除するための措置 c)個人データ処理アプリケーションに記載されているコンテンツに関連する書面、情報及び機密性の高い個人データを取り扱う際の影響評価報告書 3.個人データ保護委員会は、必須となる申請書を受け取った日から20営業日以内に、センシティブ個人データ取扱申請書を処理する。個人データ保護委員会は、センシティブ個人データ取扱申請書に含まれる情報につき確認する権利を有する。 4.次に掲げる場合において、個人データ処理者はセンシティブ個人データの取り扱いにあたって登録を要しない。 a)法律違反の防止、検出、調査、及び処分のための個人データの取扱いの場合 b)法律に従って、国家機関の医療及び社会保障機関の医療機能を実行する場合 c)裁判所の司法機能を果たす場合 d)個人データ保護委員会により認定を受けた国家機関又は科学研究組織であって、保存又は統計の目的、申請書類による調査、保存、統計目的に該当する旨の証明書を有しており;個人データが匿名化され;データ主体に影響を与える目的又は活動には使用されない場合 đ)法律で規定されているその他活動 第21条 個人データの国境を越えた移転 1.次の各号を満たす場合、ベトナム国民の個人データをベトナム領域外に移転することができる。 a)データ主体の移転への同意 b)オリジナルデータのベトナムでの保存 c)移動先の国若しくは地域、又は国若しくは地域内の特定の場所が本政令で指定されているレベル以上の個人データの保護に関する規則を発行していることに対する証明書 d)個人データ保護委員会の書面による同意 2.データ保護機関は次の場合に国境を越えた個人データの移転に対する文書を交付する。 a)本法令に基づくデータ主体の権利を効果的に保護している場合 b)国境を越えて個人データの移転を登録する際における個人データ処理者の確約 c)個人データ処理者より申請書類に記された個人データを保護するための措置 3.本条第1項を満たさない場合であっても、次の場合において個人データはベトナムの領土外に移転することができる。 a)データ主体の同意 b)個人データ保護委員会の書面による同意 c)個人データを保護するためのデータ処理者の確約 d)個人データ処理者の個人データ保護措置を適用することへの確約 4.海外に個人データを移転する個人データ処理者は、3年間、以下の内容を含む、データ移転履歴を保存するシステムを構築しなければならない。 a)個人データを外部に提供した時点 b)受領当事者の氏名、住所、連絡先情報等の受領当事者の身元 c)外部に移転される個人データの種類、数量、センシティブ性の程度 d)個人情報保護庁が指定するその他の内容 5.個人情報保護委員会は、年に一度、個人情報処理者によるベトナム国外への個人情報の移転状況を定期的に評価する。 6.次に掲げるいずれかの状況が生じた場合、国境を越えた個人データの移転を停止する。 a)個人データを処理者又は個人データ受領者が大量のデータ濫用又は漏洩を生じさせた場合 b)データ主体が自己の正当な利益を保護することが不可能又は困難である場合 c)個人データ処理者又は個人データ受領者が、個人データを保護することができない場合 7.個人データの国境を越えた移転の登録のための書類と手順は次のとおりとする a)次の詳細を含む、国境を越えた個人データの移転の申請:氏名又は名称、登録機関、事業所、居住地及び個人データを取り扱う当事者のその他連絡先情報。個人データの国境を越えた移転の法的根拠。国境を越えて個人データを移転する目的。国境を越えた移転のために登録された個人データの種類。国境を越えた移転のために登録された個人データのソース。個人データの国境を越えた移転の登録地又は場所。国境を越えて個人データを移転するための条件。個人データ保護対策の詳細な説明。 b)国境を越えた個人データ移転を申請する際の影響評価報告書。これには、国境を越えた個人データ移転の詳細な説明、国境を越えた個人データ移転の目的が含まれます。リスクと起こりうる危害の評価。そのリスク又は危害を軽減又は排除するための措置。 c)機密性の高い個人データを取り扱う際の、個人データ処理アプリケーション及び影響評価報告書に記載されているコンテンツに関連するテキスト。 8.個人データ保護委員会は、受領日から20営業日以内に個人データの国境を越えた移転の申請を処理する。個人データ保護委員会は、国境を越えた個人データの移転の登録申請書に含まれる情報情報につき確認する権利を有する。 第22条 個人データの取り扱いの規制に対する違反行為への行政違反処分 1.次のいずれかの行為に対して、5,000万ドンから8,000万ドンの罰金に処する。 a)個人データの取扱いに関するデータ主体の権利に関する規定への違反 b)個人データの開示に関する規定への違反 c)個人データへのアクセス制限に関する規定への違反 d)個人データに対するデータ主体の同意に関する規定への違反 đ)データ主体の死亡後の個人データの取り扱いに関する規定への違反 e)データ主体の同意なしに個人データを取り扱うことに関する規定に違反 g)個人データの取り扱いについてデータ主体に通知することに関する規定への違反 h)科学的研究又は統計のための個人データの取り扱いに関する規定への違反 i)自動的な個人データの取扱いに関する規定への違反 k)子供の個人データの取り扱いに関する規定への違反 l)個人データの正確性に関する規定への違反 m)個人データの保管、削除、破棄に関する規定への違反 2.次のいずれかの行為に対して、8000万ドンから10,000万ドンの罰金に処する。 a)技術的措置を適用せず、個人データの保護に関する規程を制定しない行為 b)センシティブな個人データの取り扱いの登録に関する規定への違反 c)国境を越えた個人データの移転に関する規定への違反 d)本条第1項に規定された行為に対する2回目の規定行為 3.次の行為に対して、ベトナムで個人情報漏えいを処理する党の総収入の最大5%の罰金に処する。 a)本条第1項に規定する行為に対する3回目の違反行為 b)本条第2項のポイントa)、b)、c)で指定された行為に対する2回目の違反行為 4.追加の罰則 a)本条第2項に規定された違反については、個人データの取扱いを1か月から3か月の間停止する b)センシティブ個人データの取扱い及びベトナムの領土の境界を越えて個人データの移転に関する同意書を剥奪する 5.是正措置:本条第1項及び第2項に規定された違反を犯したことにより得られた金銭を没収する。 6.公安省のサイバーセキュリティ及びハイテク犯罪防止及び管理部門の局長は、本条の第1、2、3、4、5項に規定される行政違反に対して罰則を科す権限を有する。

【必見】第1回 ベトナム個人情報保護法 ~適用対象、同意関連~
はじめに 現在ベトナムでは、個人情報保護法の制定作業が進められています。現在その草案が公表されており、この度、弊所にて草案の翻訳文を公表することとなりました。 第1回では冒頭部分で重要となる、本法令の適用関係に関する注意点、個人情報取得に関する注意点を解説いたします。 適用対象(主体)について まず、本法令は2条8項において「個人データ処理者とは、個人データ処理活動を行う国内外の機関、組織、個人」と定義しています。日本法でいうところの個人情報取扱事業者に相当するものと考えられますが、日本の場合は、個人情報(正確には「個人情報データベース等」)を事業用に供する者を指すとしており、事業としてではない個人情報の取扱いについて規制を行うものではないことが分かります。これは、例えば友人を紹介する場合などに個人情報の第三者との共有などと考え、個人情報保護法を適用しようとすれば、いかに不都合が生じるかということからもその理由は容易に分かるかと思います。 他方で、ベトナムの草案では、このような個人情報取扱事業者(業として取扱う者)とそうでない者とを区別していません。解釈運用上、事業者が適用対象となることが想定されますが、注意は必要です。 適用対象個人情報(客体)について 次に個人情報(客体)ですが、ベトナムでは、個人データという用語を用いており、全体で同用語を用いた制度体系を構築しています。これがどういうことかと言いますと、日本では個人情報と主に電子計算機等で処理する個人情報を区別し、後者を個人情報データベース等として異なる規律で構成しています。前者の場合、利用目的規制等はありますが、安全管理措置や第三者提供の制限は受けない扱いになっています(例として、日本法の16条は「個人情報」を取り扱ってはならない、20条、23条は「個人データ」に対する規制として規定されており、個人情報が意図的に除外されています)。 ベトナムでは日本のような区別がなく、個人情報であれ、電子計算機等で処理する個人情報であれ同様の規制に服することが予定されています。そのため、規制対象範囲としては日本法のそれよりも広いこととなり、紙面媒体等での従業員連絡先名簿や社員の経歴書などであっても本法令全体の規制を受ける点に注意しなければなりません。 要配慮個人情報(センシティブ情報) さらに個人情報の内容を細かく見ると、本政令2条2項及び3項により、日本と同様、一般的な個人情報とより厳しい規制が課せられる個人情報との2重構造を予定していることが分かります。日本でいう要配慮個人情報と概ね範囲は一致しているものと思われます。昨今において特に注意が必要なものは、従業員のコロナワクチン接種証明関係やコロナ罹患歴などが挙げられます。また、日本と異なり位置情報のような必ずしも本人の社会的地位等と関係性のない項目などが含まれている点に注意が必要であり、スマートフォンAppsにて位置情報を用いる場合などは本項目が大きな影響を与える余地も考えられます。 要配慮個人情報(センシティブ情報)に該当する場合、当該情報取得の際、説明義務が課せられており(本法令8条5項)、通常の個人情報よりも取得の段階等に強い規制が置かれています。現在の草案の段階では、この説明の具体的内容は明記されておらず、定型的な説明文の提示で足りるのか、質疑応答のような形で、コミュニケーションの機会までデータ主体に対して行う必要があるのか明示されていません。現在の事業で要配慮個人情報(センシティブ情報)を取り扱っている事業者は、この点について法令等をよく確認の上、十分な準備を行っておく必要がありそうです。 個人情報取得時の同意 個人情報取得の際には、本人の同意取得が必要とされています。日本法では17条2項の規程により、要配慮個人情報に限り本人の同意が必要とされています。しかしながら、ベトナムの場合、本法令8条にあるよう、個人情報の性格を問わず、本人同意が必要とされています。その結果、通常の個人情報であっても、本法令の施行に応じて改めて従業員等から同意を取得することが必要となる可能性が高く、取得範囲の規模によっては相応の準備が必要となります。 同意に関する規制としては、黙示同意などの消極的な方法による同意が認められていないことと、要配慮人情報(センシティブ情報)については本人への説明が必要とされていること、いずれの同意についても、書面の形で同意取得した旨、事後的に確認できる方式で取得する必要があります。この規制により、例えば、従業員に対する一斉説明会を行い、不同意の者は追ってその旨連絡するような方法は採れず、他にも口頭の方法による個人情報の取得については、同意取得のリスクを取得者側が負うこととなります(口頭同意がある場合、同意はあるのですが、事後的に同意取得を示すことができず、同意不取得による罰則等のリスクを負うこととなります)。 その他、データ主体の同意には条件を設けることができる旨規定があり、この条件を付された同意がなされた場合、続く本法令11条3項の個人情報の取扱いに関する通知を省くことができなくなります。そのため、個人情報取得者側としては、可能な限りそのような条件が同意に付されることを避ける必要があるということになりますが、そのためには同意取得の際に情報主体者の十分な理解を得ることが密接に関係し、結果、丁寧な説明と場合に応じて質疑応答の機会を設ける必要が出てきます。 取得した同意は続く各規制のうち、同意があることで免責が生じる場合における最大の防御方法となります。そのため、単純に「個人情報の取得に同意します」という三行半の同意書を取得していた場合、その後の利用態様や責任追及の場面においては予定していた免責効果を得られないリスクが考えられます。 制定法令に適切に対応するために 弊所では、この度の個人情報保護法に対応するためのパッケージサービスを提供しております。現地法人で用いることができる日越語のプライバシーポリシー(個人情報規程)モデル案のご提供や、制定個人情報保護法に関するコメント、注意点や制定法対応のために企業が行うべきことのリーガルコンサルティング、草案のバージョンアップや法令が制定された場合のアフターフォローなどが含まれるサービスとなります。 もちろん、現在日本で用いているプライバシーポリシーのローカライズやベトナム語への翻訳、従業員などに対する説明会の実施なども提供しております。 本法令対応が重要であることは分かったけれども、自社の負担をできるだけ軽減したいと思ってらっしゃる企業様におかれましてはお気軽にご相談いただけますと幸いです。 政府 番号: /2021/NĐ-CP 草案 2ベトナム社会主義共和国 独立・自由・幸福 ハノイ、2021年●月●日 草案2 政令 個人データの保護に関する規制 2015年6月19日の政府機関組織法に基づき; 2015年11月24日の民法に基づき; 2004年12月3日の国家安全保障法に基づき; 2018年6月12日のサイバーセキュリティ法に基づき; 2020年11月13日の行政違反処理法に基づき; 公安大臣の提案で、 政府は、個人データの保護規制する法令を公布する 第1章 一般規制 第1条 調整範囲と対象適用 1.この政令は、個人データ、個人データの取扱い、個人データの保護方法、個人データ保護委員会、個人データ違反の処理、関連のある機関・組織・個人の個人データ保護責任を規定する。 2.この政令は、個人データに関連する機関・組織・個人に適用される。 第2条 用語説明 この政令では、次の用語は次のように解釈される。 1.個人データとは、個人に関するデータ、特定個人の確定又は確定可能性に関連するデータをいう。 2.基本個人データは次のものを含む。 a)氏、ミドルネーム及び出生名、別名(ある場合) b)生年月日;死亡・行方不明時の年月日 c)血液型、性別 d)出生地、出生地登録、居住地、現在地、出身地、連絡先住所、電子メールアドレス đ)学歴 e)民族 g)国籍 h)電話番号 i)身分証明書番号、パスポート番号、市民識別番号、運転免許証番号、ナンバープレート番号、個人税コード番号、社会保険番号 k)婚姻状況 l)サイバースペースでの活動又は活動履歴を反映するデータ 3.センシティブ個人データは次のものを含む。 a)政治的・宗教的主張について個人データ b)健康状況の個人データとは、データの主体の身体的又は精神的な健康状態に関連する情報、登録プロセス又は医療サービスの提供中に確定・収集されたというものをいう c)遺伝的個人データとは、個人が受け継ぎ、又は獲得した遺伝的特徴に関連する情報をいう d)生体認証の個人データとは、各個人の物理的特性・生物学的特性に関する情報をいう đ)性別状況に関する個人データとは、男性、女性、女性と男性の組み合わせ、完全に女性ではない若しくは完全に男性ではない、女性でも男性でもないという性別が確定される人の情報、又は出生時に確定された性別に適合しない性別を意識した主体の状態をいう e)生活、性的指向に関する個人データ g)法執行機関によって収集・保存された犯罪行為に関する個人データ h)財務について個人データとは、金融機関がデータ主体から提供された口座、カード、支払い手段を確定するために使用される情報又は金融機関、元金データ、データの主体との関係に関する情報をいい、書類、財務状況、信用履歴、収入レベルなどを含むものをいう i)位置についての個人データとは、個人の過去及び現在における現在位置情報をいう k)社会関係についての個人データ l)法律によって情報である旨指定され、保護措置が必要とされるその他個人データ 4.個人データ保護とは、個人データに関する法律の規定に違反する行為を予防、検出、防止、処理する措置をいう。 5.データの主体とは、個人データが反映する個人をいう。 6.個人データ処理とは、個人データに影響を与える一つ又は複数の行為をいい、個人データを収集、保存、変更、開示、アクセスを承認、取得、回収、リコール、復号化、コピー、移転、削除、破壊する行為を含む。 7.個人データの保護権利とは、個人データを保護するために個人が行使することのできる権利又は個人が各機関・組織・個人に対し自分の個人データに対する尊重又は保護措置を講じるよう要求することができる権利をいう。 8.個人データ処理者とは、個人データ処理活動を行う国内外の機関、組織、個人をいう。 9.第三者とは、個人データ処理者やデータの主体以外の個人データを受領し、個人データ処理活動を行う国内外の機関、組織、個人をいう。 10.個人データの自動処理とは、コンピューターシステムを用いたアルゴリズムを通じて個人データを処理することをいう。 11.国境を越えたデータ移転とは、サイバースペース又は電子的設備の使用を通じてベトナム国民の個人データをベトナム社会主義共和国の領土外に移転する行為をいう。 12.オリジナルデータは、個人データ処理者が未だ処理及び第三者移転していない初期のバージョンデータをいう。 13.個人データの匿名化とは、識別子の各内容を匿名化し、若しくは削除する、又は他架空の名前・コードに差し替えることで特定の個人について確認することができない新データ作成プロセスをいう。 14.個人データの匿名化とは、個人データを新しく不可逆的な形式のデータに変換するプロセスをいう。 15.個人データに関する規制への違反とは、個人データ処理に関してあらゆる違法的な行為をいう。 第3条 個人データ保護規則 1.法的原則:個人データは、法律に従って必要な場合においてのみ収集される。 2.目的原則:個人データは、登録された目的、個人情報の処理に関する宣言に従ってのみ処理される。 3.最小化原則:個人データは、明確化された目的を達成するために必要な範囲に限り収集される。 4.限定使用原則:個人データは、データの主体の同意がある場合又は法律に従って権限を有する機関の許可を得た場合においてのみ使用される。 5.データ品質原則:個人データは、データ処理の目的を確実に達するために完全に更新する必要がある。 6.セキュリティ原則:個人データの処理中に個人データ保護措置が適用されなければならない。 7.プライバシー原則:データの主体は、自分の個人データ処理に関する活動を認識し、関連する通知を受け取る権利を有する。 8.保護原則:データ処理中に個人データは保護されなければならない。 第4条 個人データの保護規制への違反の処理 1.個人データ保護規制に違反した機関や組織は、違反の程度に応じて行政処分又は刑事処分を科せられ、法律に従った追加処分が適用される場合がある。 2.個人データ保護規制への違反処理は、ベトナムにおける事業活動がある国内外の全ての組織、企業、個人に適用される。 3.本政令に定める罰金の他、個人データ処理者が複数回違反を犯し、重大な結果を生じさせたときは、個人データ処理者のベトナムにおける総収入の最大5%に相当する罰金を科せられる場合がある。 第2章 個人データ取扱い 第5条. 個人データの取扱いに関するデータ主体の権利 1.法令に別段の定めがある場合を除き、個人データの処理者、第三者に対して自己の個人データの取扱いを同意又は不同意を行うことができる。 2.取扱時点又は通知をすることができる時点において、直ちに個人データの処理者から通知を受領することができる。 3.個人データ処理者に対して、自己の個人データの訂正、拝見、コピーの提供を求めることができる。 4.法令に別段の定めがある場合を除き、個人データの処理者に対して、個人データの取扱いの終了、個人データへアクセスする権利の制限、個人データの開示若しくは個人データへのアクセスの許可の終了、収集した個人データの削除又は閉鎖を求めることができる。 5.次に掲げる場合に、法令の定めに従い異議を申し立て、又は個人データ保護委員会に異議を申し立てることができる。 a)自己の個人データが侵害された場合 b)自己の個人データが目的、合意した内容又は法令の定めに適合しない態様で取り扱われた場合 c)自己の個人データに関する権限が侵害された又は不適切な取扱いの場合 đ)自己の個人データが侵害された根拠がある場合であって、法令の定めに従い損害賠償を求める場合 第6条 個人データの開示 1.個人データの処理者、第三者は、次に掲げる場合においてデータ主体の同意を取得することなく個人データを開示することができる。 a)法令の定めに従う場合 b)情報の開示が国家の利益・安全、社会の秩序・安全のために必要である場合 c)個人データが国防、国家安全、社会秩序・安全、社会道徳、コミュニティの健康のためにメディアで開示する場合 d)個人データをデータ主体に対して経済的、名誉的、精神的、物質的に損害を与えない方法で新聞法の定めに従いメディアで開示する場合 đ)緊急かつデータ主体の生命への脅威又はデータ主体の健康若しくはコミュニティの健康に深刻な影響を与えるリスクがあると別途法令が定める場合 2.本条1項に定める場合を除き、データ主体が求めるときは、個人データの処理者、第三者は個人データ開示を直ちに終了させなければならない。 3.次に掲げる場合において他人の個人データを開示を行ってはならない。 a)当該個人データがセンシティブ個人データである場合 b)個人データ主体の適法な権利に損害を与える場合 4.法令に規定された権限を有する国家機関の公共での録音、録画、その録音、録画から収集したデータの取扱いはそのデータ主体の同意を取得したものとみなす。 a)収集機関は、データ主体自らが録音、録画され、その個人データを取り扱われることを認識し、いつでもその停止を求めることができる旨をデータ主体に対して通知しなければならない b)国防、国家安全、社会秩序・安全、社会道徳、コミュニティの健康を目的とする場合は、通知をすることを要しない 第7条 個人データへのアクセスの制限 次に掲げる場合において個人データの処理者は個人データの主体ではない対象の個人データへのアクセスを制限しなければならない。 1.国家の利益・安全、社会秩序・安全に悪影響を与える場合。 2.他の組織、個人の適法な権利、利益に影響を与える場合。 3.法令の定めに反し第三者に個人データを開示し、共有する場合。 4.他人のプライバシー権、自由権に影響を与える場合。 5.法令に違反した行為の調査又は処分過程に影響を与える場合。 第8条 個人データに対するデータ主体の同意 1.自己の個人データの取扱いを許可を内容とするデータ主体の同意は、自由かつ次のの内容の理解がなければ効力を有しない。 a)取り扱われる個人データの種類 b)個人データの取扱いの目的 c)個人データの取扱対象、共有をできる対象 d)第三者に個人データを譲渡し、共有する条件 đ)法令に定める自己の個人データの取扱いに関するデータ主体の権利 2.データ主体の沈黙又は黙示は同意。 3.データ主体は一部的に同意し、又は条件を付けて同意することができる。 4.データ主体の同意は印刷し、文章でコピーできる形で表現されなければならない。 5.データ主体に対して、取扱う必要があるデータがセンシティブな個人データである場合、その旨説明を行わなければならず、データ主体の同意は印刷し、文章でコピーできる形で表現されなければならない。 6.国家活動により取得された個人データにおけるデータ主体の同意は、データ主体が別段の意思を表示した場合を除き、データ主体の存在期間に加えてデータ主体が死亡した時点から20年間にかけて効力を有する。 7.データ主体は、自己の同意をいつでも撤回することができる。 8.紛争が生じた場合、個人データの処理者はデータ主体の同意を証明しなければならない。 第9条 データ主体が死亡した後の個人データの取扱い 1.データ主体が死亡後、遺言又は法令に定める相続人の文章での同意が、データ主体と個人データの処理者との間の合意と異なる場合、そのデータ主体に関する個人データの取扱いは、その遺言又は相続人が行った同意及び本政令第6条及び前条に従う。 2.前項の規定は、取扱われる個人データに氏名、性別、生年月日、死亡の年月日、失踪の年月日及び死亡原因のみ含む場合、適用しない。 第10条 データ主体の同意がない場合における個人データの取扱い 1.次に掲げる場合において個人データはデータ主体の同意を要せず取り扱うことができる。 a)法令の定める場合 b)国家の利益・安全、社会秩序・安全を目的とする場合 c)緊急かつ、データ主体の生命への脅威、又はデータ主体の健康又はコミュニティの健康に深刻な影響を与えるリスクがある旨法令が定める場合 d)法令に違反した行為の調査、処分を目的とする場合 đ)ベトナムが加盟する国際合意、国際条約においてデータ主体の同意を要せず個人データの取扱いが許容される旨明記する条項に基づく場合 e)本政令の第12条に基づき科学研究又は統計業務を目的として個人データを取り扱う場合 2.次に掲げる場合は、データ主体の承諾を要せず第三者に個人データを共有し、又は個人データへのアクセスを提供することができる。 a)法令又はベトナムが加盟する国際協定又は国際条約に従う場合 b)データ主体の生命、健康又は自由を保護する場合 c)データ主体の権利と利益に影響を与えず、データ主体の承諾を得ることが不可能である場合 d)本政令第12条に基づく科学研究又は統計を目的として個人データを取扱う場合。 第11条 個人データの取扱いについてデータ主体への通知 1.本条3項に規定される場合又は法令に異なる規定がある場合を除き、一切の個人データを取り扱う行為はデータ主体に通知されなければならない。 2.個人データ取扱いに関するデータ主体への通知内容。 a)個人データの処理者の情報 b)取り扱われる個人データの種類と取扱方法 c)取扱時間、取扱目的 d)特殊な状況で取扱われる個人データの種類又は特殊な取扱いの目的が重大な危害のリスクを生み出す可能性がある場合はその旨。 đ)データ主体の権利及び権利を行使する手続 e)個人データ保護委員会により実施される個人データ保護の信頼性評価 g)ベトナムの領土外への個人データ移転に関する情報 h)規定されるその他情報 3.次に掲げる場合において、個人データの処理者は個人データ取扱いに関する通知することを要しない。 a)データ主体が個人データの取扱いの内容、活動に完全に同意した場合 b)個人データ取扱いが法令、国際協定、国際条約により規定される場合 c)データ主体の利益に影響せずデータ主体に通知することが不可能である場合 d)本政令第12条に基づく科学研究又は統計を目的として個人データを取扱う場合

ベトナム駐在員弁護士によるベトナム法解説~ベトナム上場株投資の注意点~
現在、堅調なベトナム経済を背景に、ベトナム上場株式への投資が、日本の個人・法人を問わず、徐々に増加している状況です。このようなベトナム上場株式の取引では、多くの場合には投資信託などに組み込まれた商品の取引や、法的に問題の生じない少額の取引が多いため、特段問題が生じることが多くないのですが、大口の取引についてはベトナム証券法等の各種規制により、日本人又は日系企業についても罰則等を課された事例もあります。そのため、ベトナム証券法についての規制を把握することは重要といえます。 そこで、本稿では、ベトナム証券法の規制について基本的な内容を弁護士の盛一也が解説します。 大量報告規制について ベトナム証券法では、日本と類似の大量保有報告規制が設けられています。具体的には、公開会社について直接又は間接的に発行会社の議決権の5%以上の株式を保有することになった株主などは、当該公開会社、証券取引委員会及び証券取引所などに大量保有報告書を提出する必要があります。また、大量保有報告書の記載事項に重要な変更が生じた場合や、議決権割合が1%を超えて壮言した場合などに追加報告書を提出する必要があります。 日系企業等の例について 2018年8月15日、国家証券委員会(SSC)の監察官は、日本のアイザワ証券に対する行政違反の制裁に関する決定No.206/QD-XPVPHCを発行しました(住所: 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング)。具体的には以下の通りです。 同社は、ベトナムの上場会社であるVisaco(VMI)株について、4.86%から5.58%、6.31%に持株を増やす等の取引を行った際に報告を届けたものの、内容に誤りがあった等により、政府令第1項第27条、2013年9月23日付のND-CP、法令第108/2013/ND-CP)は、政府令第145条第1項第1項第1項、2016年11月1日、法令第108/2013/ND-CP(法令第145/2016/ND-CP)等により、1,000万VND(≒5万円)の罰金が科されました。 インサイダー取引規制について ベトナム証券法等では、日本と同様にインサイダー取引規制が設けられています。具体的には、①自己又は他人のためにインサイダー情報を利用して証券の売買を行うこと②意図があるかを問わず、インサイダー情報を他人に提供すること③意図があるかを問わず、インサイダー情報に基づき他人に証券の売買に関する助言をすることなどが禁止されています。 また、インサイダー取引に対する行政罰金は、違法に取得した収入の10倍となり高額ですし、違反行為の重大性により、違反者は刑事処分を受ける可能性もあります(個人に対しては、6か月から7年以下の懲役に処し、法人に対しては、1年以上3年以下の期間、一定の領域における事業の禁止又は1年以上3年以下の期間について、資金調達の禁止の措置が適用されることがあります。) ただし、ベトナムの証券市場では、取り締まられていないインサイダー取引も多く、今後の課題となっております。 相場操縦規制について インサイダー取引と同様に、相場操作も証券法の規定に対する重大な違反であり、違反程度に応じて行政罰又は刑事処分が科されます。ベトナムにおいて、相場操縦とは、①虚偽の需要、供給を作り出すために、自己又は他人の一つ又は複数の取引口座を使用するか、互いに共謀して証券を売買すること②他人と結託し、他人を引き入れる形式で証券の売買注文を行い、証券価格を操作すること③証券価格を操作するために他の取引方法を組み合わせて使用したり、誤った噂を広めたりすることなどを意味するとされています。 相場操縦行為についての行政処分と刑事処分は、インサイダー取引の場合と同様です。 インサイダーと相場操縦の具体例 ベトナムにおける報道等によると、上場企業の経営に関与している者が世間に公開前の情報を外部に漏らし、また、他者と連携して相場操縦を行うことで、市場を欺くことは多くみられるとのことです。ただし、インサイダー取引や相場操縦について、具体的に行政や刑事罰を受けることは、その証明が困難であるため、行政罰金又は刑事処分が課せられたケース、特にインサイダーのケースはかなり少ないようです。 ベトナム人の例にはなりますが、2020年7月に、国家証券委員会(SSE)の検査官は、ホーチミン証券取引所(HoSE)に上場しているCity Auto JSCのCTF株を操作し、また、22の口座を使用して取引した行為に対し、ホーチミン市のタンタンドグループ株式会社に12億VND(≒600万円)、ドン・ゴ・ヴァン・クオン氏に5億5000万VND(≒275万円)の罰金を科す決定を下しました。 まとめ 最後に、ベトナム経済の好調は今後も継続することが見込まれており、株式投資だけでなく、ベトナムに法人を設立し事業を営む企業も着実に増加しています。弊所ホーチミンオフィスでは、ベトナムへ進出を検討されている企業様の相談を随時承っておりますので、ご関心がある皆様は随時お問い合わせ(secretary-vn@meilin-int.com)いただけますと幸いです。

日系企業必見!【最新版】ベトナムプライバシーポリシー(個人情報保護法)改訂
現在、ベトナムで初めてとなる個人情報保護法の制定準備が行われています。2022年以降の施行になると思われ、間違いなく来年影響を与える法令の筆頭になると見込まれます。本記事では、個人情報保護法改正案の内容の解説と企業がすべきアクションプラン、最後に弊所のプライバシーポリシー(個人情報規程)改訂のパッケージサービスをご紹介いたします。 個人情報取得のポイント 現在の草案第8条に個人情報取得に関する条文が置かれています。同条では、個人情報の種類、情報処理目的、共有される場合の共有相手や共有条件、個人情報主体の権利等について理解を得る必要がある旨規定があります。これら項目について草案は、いわゆる黙示の方法による同意を認めておらず、明示同意の取得が求められています。また、当該同意取得は、原則として書面によってなされることが予定されています。電子的方法での同意取得も可能ですが、ECサイトやアプリなどから個人情報を取得する場合は、明示性との関係で慎重な検討が必要でしょう。電子媒体等で取得を行う場合は、当該同意取得について書面媒体に印刷などの方法にて落とし込む必要があることが予定されています。また、当該書面は、個人情報取得者の同意取得証明資料として用いられることが予定されており、個人情報を紙媒体で取得した場合も、当該書面の保管などについて負担が生じることが想定されます。 その他、従業員関係にて同意を取得する場合、社員向け個人情報取り扱い説明会を行う企業も今後出てくると思われます。従業員数が一定規模以上の場合、同意取得だけでも従業員からの質疑応答や同意を拒絶する従業員への対応の検討など、相応の準備が必要となってくるため注意が必要です。 要配慮個人情報(センシティブ情報)と域外移転 ベトナムでの個人情報保護法でも、個人情報の定義を基本的な個人情報と個人の人格等に密接に結びつく個人情報を区別しており、後者は日本法にいう要配慮個人情報(センシティブ情報)に相当します。昨今のコロナ禍の影響で、今後コロナウイルスワクチン接種率が高まってくると思われ、従業員や入店客などのワクチン接種状況の情報はこの要配慮個人情報における「健康、医療に関する情報」に該当すると思われます。その結果、例えば勤務従業員について工場エリア等の関係から、ワクチン接種者でなければ勤務できない場合や出張にはワクチン接種証明が必要とされる場合などにおいて、雇用企業側は従業員のワクチン接種状況を把握しておく必要があり、要配慮個人情報(センシティブ情報)を取り扱っていく必要が出てきます。この要配慮個人情報(センシティブ情報)は、当然に通常の個人情報よりも厳しい取扱いが求められており、その中でも、草案に規定されている要配慮個人情報の使用前登録義務が挙げられます。これは、要配慮個人情報についてはその目的使用前に政府当局に登録を行う必要がある旨規定を置いているものであり、理屈上、企業側は上記のような必要が生じた場合は、登録を行わなければ従業員のワクチン接種有無を確認できないということになりかねません。草案上の想定処理期間は約20日以内とされていますが、実運用上は1か月あたりを見ておいた方が良いかと思われます。また、このような登録個人情報は政府側が登録により閲覧可能となるため、個人情報主体のプライバシーにも配慮が必要となってきます。前述の個人情報取得について同意をしない従業員対応などはこのような事由を背景とするものも想定されます。 日本本社との連携 ベトナムで取得した個人情報を日本本社などの海外に移転させる場合、いわゆるデータローカライゼーションが行われなければならない旨の規定が置かれています。これにより、個人情報を移転する場合、移転先国(地域)の個人情報保護水準を確認する必要が出るだけではなく、元データについては常にベトナムに保管等されておく必要があります。加えて、データ移転には政府当局による承認が必要となっており、これもまた移転についての手続について企業の負担になってくる点が予想されます。 企業のとるべきアクションプラン 企業が採るべき最初のアクションは現在ベトナム現地法人が扱っている個人情報の項目と使用目的の洗い出しと確認になります。特に要配慮個人情報(センシティブ情報)については登録申請の手続を要するため、どのような情報について申請を行わなければならないかという点や個人情報主体(従業員など)に対する説明の際に、どのような情報がどのような目的で使われているのか明示するための資料準備を行うことになります。また、併せて従業員の温度感などから同意に反対する個人情報主体が現れた場合の対応方針について議論を重ねることも有効です。 次に同意取得に向けた説明資料の準備と自社のプライバシーポリシー(個人情報規程)の見直しです。現在日本でプライバシーポリシーなどを作成している企業においては、この度の制定されるベトナムの個人情報保護法への適合性を図る作業が必要となってきます。 ベトナム明倫国際法律事務所のサービスパッケージ 弊所では、個人情報保護法対策として、ベトナム版のプライバシーポリシー(ベトナム語/日本語併記)を作成し、あわせて各条項についてのワンポイントアドバイスを併記したプライバシーポリシーパッケージを提供しております。また、クライアント様のご希望に応じてプライバシーポリシー作成や運用に向けたコンサルティングも行っており、従業員説明会で用いる資料(紙媒体や動画)や運用上のトラブルシューティングを行うことができ、現地駐在員の貴重なリソースを大幅に節約することができます。 ご興味のある方(企業様)は、secretary-vn@meilin-int.comまでお問い合わせください。 終わりに いかがでしたでしょうか。数年前に日本でも起きたGDPRの影響がとうとうベトナムでも生じることとなりました。個人情報の取扱いはコンプライアンス上も業務効率化上も重要な情報となりますので、この度の個人情報保護法制定と適切に向き合っていきたいですね。 (弊所では個人情報保護法だけではなく、様々な法令に対応する顧問契約サービスも提供しております。ご興味のある方は、secretary-vn@meilin-int.comまでお問い合わせください。)

ベトナム駐在員弁護士による駐在員レポート~ホーチミン市における社会経済活動の今~
現在ベトナムへの入国についてはワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)を用いることで入国時の集中隔離期間を短縮することができます。これにより、ベトナムへの渡航コスト削減や渡航スケジュールの短縮化を図ることができます。 他方で、ベトナム現地の規制が目まぐるしく変わることもあり、ベトナム現地の状況が見えにくくなっております。そのため、日系企業の皆様が、ベトナム現地の状況を把握し、ベトナム進出のタイミングについて判断する材料が少ないと感じているかと思います。 そこで、本稿では、ベトナム進出を判断する上で重要となるベトナム現地の状況について弁護士の盛一也がレポートします。 ホーチミン市内におけるオフィス勤務の再開について ホーチミン市人民委員会は、9月30日付で「ホーチミン市におけるCOVID-19感染防止対策の継続的管理と調整及び経済社会の順次回復と発展」(No.18/CT-UBND号)(以下、「指令18」といいます。)を発し、10月1日(金)より、長らく続いた社会的隔離措置が緩和されることになりました。 これに伴い、弊所ホーチミンオフィスでは、7月9日(金)から約3か月続いた在宅勤務から、10月4日(月)より、オフィス勤務を再開いたしました。いわゆる5K(マスク着用、消毒の履行、他人との間隔を保つこと、多人数の集合の禁止、健康申告の履行)に十分留意したうえで、試行的に業務を行っております。また、弊所が入居している、ベトナムローカルの企業(ロジスティックス関連の会社や法律事務所)についても、同様にオフィスワークを再開しているようです。 ホーチミン市内における移動手段の制限 他方で、移動手段(タクシーやGrab)が制限されており、多くの企業(ローカル・外資のいずれも含む。)では、在宅勤務を継続しているようです。幸いにも、弊所では、私を含めたスタッフの全員が職場から徒歩圏内に居住しているため、通勤自体に問題は生じておりませんが、バイク等を保有しない多くの外国人にとって交通手段を欠く状況が一定程度続くものと予想されます。 なお、ホーチミン市内では10月5日(火)より一部タクシーの再開、10月7日(木)にはGrab(バイクを含まない。)の再開がありましたが、ドライバーはワクチン接種を済ませるだけでなく、定期的な新型コロナ検査による陰性を示すことが営業の条件となっており、ドライバーは従前よりも大幅に少ない状況です。 ホーチミン市内の社会活動・経済活動 筆者は、社会的隔離措置終了後、徒歩で通勤をしていますが、夕方の帰宅時には公園等でランニングや運動をするベトナム人や欧米人が増加しているように思えます。街の人手が増えるだけでなく、通勤途中に見かける店舗についても日に日に営業を再開するものが増えているようです。 また、ハノイ市、ダナン市では既に飲食店での店内飲食が再開しており、ホーチミン市においては、慎重な検討がなされるとされていますが、今後、同様に店内飲食が再開されることが期待されています。 他省等からホーチミン市への移動 ホーチミン近郊の工場では、「3つの現場」と呼ばれる、現場での生産、現場での食事、現場での休憩・宿泊体制を守る場合に運営が可能になっていましたが、このような運用についても指令18等により、緩和が進んでいるようです。具体的には、新型コロナワクチンを1回以上接種していれば、付近の省からホーチミン市に入ることが可能になりました。 なお、このような工場においては宿泊等の施設がないことから、地面や薄手のマットレスで睡眠を取る駐在員も多く、シャワーについても水しか出ないというケースも多いようです。 ホーチミン駐在弁護士による入国・ベトナム進出サポート 最後に、弊所ホーチミンオフィスでは新型コロナ後を見据えて、ベトナムへ進出を検討されている企業様の相談を随時承っておりますので、ご関心がある皆様はsecretary-vn@meilin-int.comまで お問い合わせいただけますと幸いです。
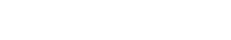
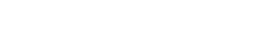
 ベトナム情報ニュースレター(無料)申込
ベトナム情報ニュースレター(無料)申込